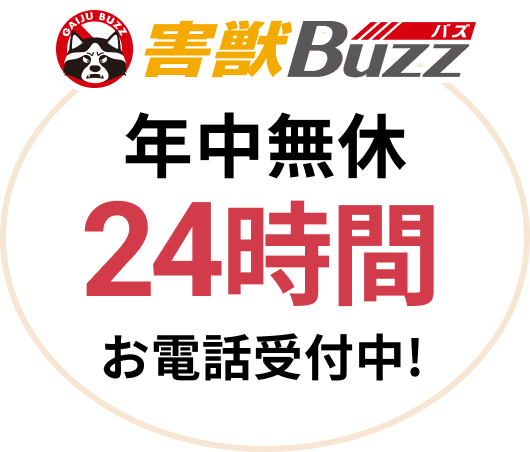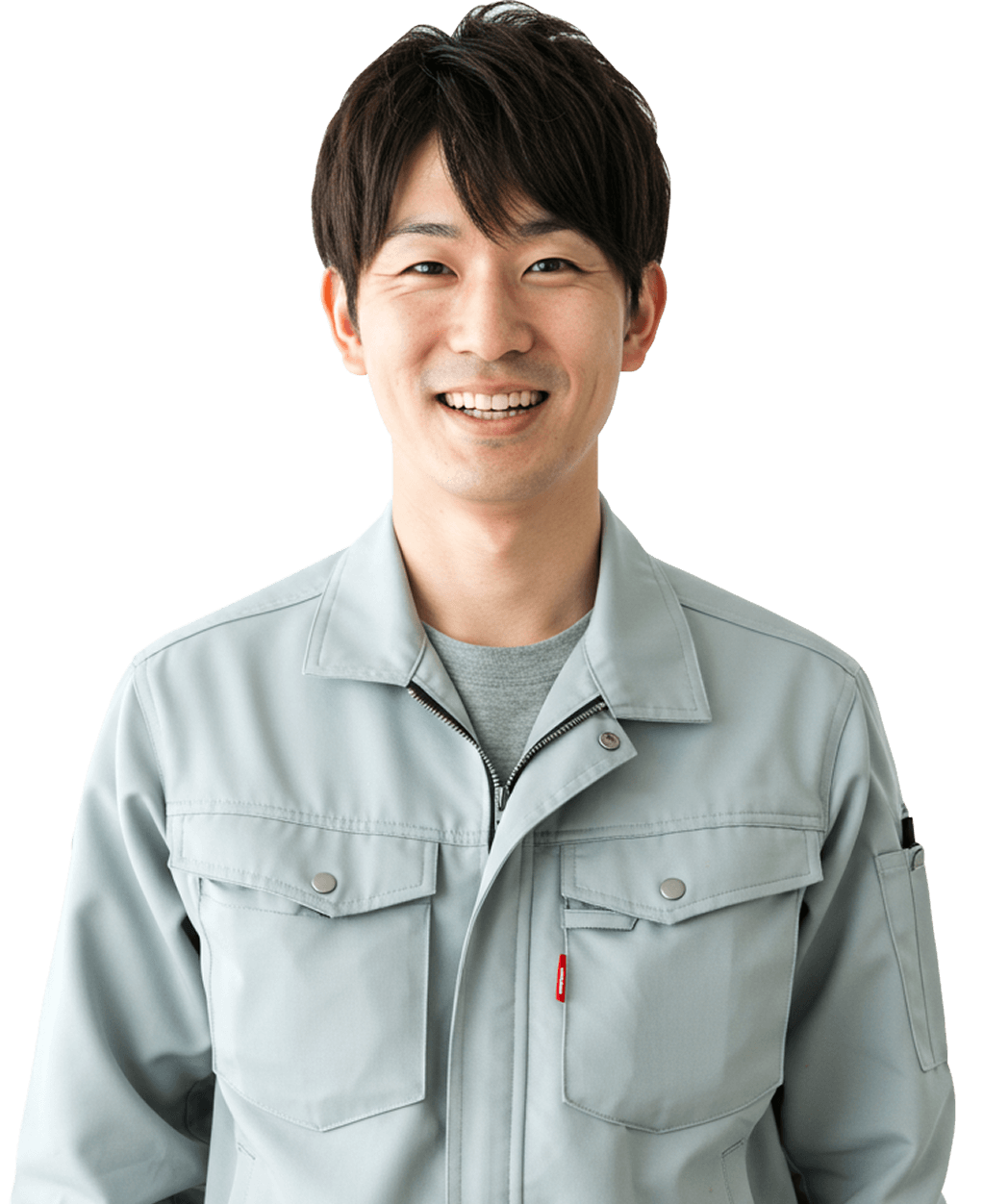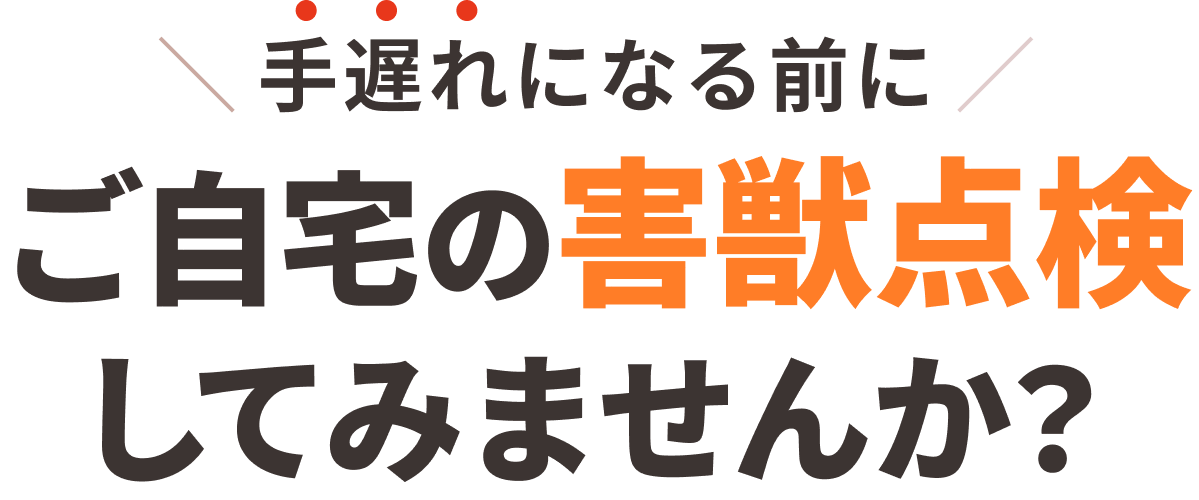ムクドリのフンはこう見分ける!特徴から片づけ方まで徹底解説!

「ベランダや車、自宅の軒先などに大量のフンが落ちていて、掃除をしてもすぐにまた汚れてしまう」そんなストレスを抱える方は少なくありません。そのフンがムクドリの場合、悪臭や建物の劣化などを引き起こす原因になることもあります。
本記事では、ムクドリのフンの特徴や安全な片付け方、効果的な予防策までを分かりやすく解説します。ムクドリによる被害を防ぎ、快適に生活できるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
ムクドリのフンの特徴を解説

ムクドリのフン被害を適切に対処するには、まずその特徴を知ることが大切です。ムクドリのフンの色や形状には特徴があり、また「なぜ同じ場所に大量のフンが落ちているのか?」といった疑問にも理由があります。
ここからは、ムクドリのフンの色と形状、そして大量のフンが同じ位置にある理由について詳しく解説します。
フンの色と形状
ムクドリのフンは「白と黒が混ざったペースト状」であるのが特徴です。
白い部分は尿酸で、黒い部分が未消化の食べ物の残り(便)です。フンは液状に近いことが多く、乾くと固まってこびりつくため、掃除がとても面倒になります。特に車やベランダに落ちると、時間の経過とともにシミや腐食を引き起こす原因になります。
乾燥する前であれば比較的簡単にフンを落とせますが、放置してしまうと高圧洗浄機や強力な洗剤が必要になるケースもあるため、早めに対応することが大切です。
大量のフンが同じ位置にある理由
ムクドリは「ねぐら」と呼ばれる決まった場所で集団で寝泊まりする習性があります。
このねぐらに選ばれやすいのが、街路樹、公園の木、電線の上、建物のひさしなどです。同じ群れが何日も同じ場所に集まるため、その下にフンが集中し、短期間で大量に溜まっていきます。
さらに、ムクドリは帰巣本能が強く、一度ねぐらに選んだ場所には強い執着を持ちます。そのため、人が追い払おうとしても、なかなかその場所を離れようとしません。この習性が、ムクドリのフン被害を長引かせる大きな原因のひとつです。
参考:農業・食品産業技術総合研究機構「鳥種別生態と防除の概要:ムクドリ」
ムクドリのフンを片付ける手順

ムクドリのフンには病原菌が含まれているため、清掃時には正しく安全に片付けることが大切です。しかし、ただ拭き取るだけでは菌やニオイが残ってしまうこともあり、慎重に作業する必要があります。
ここからは、フンの片付けに必要な準備から具体的な掃除の手順、注意点までを分かりやすく解説します。
マスクと手袋を着用
まずは防護対策として、マスクと手袋を必ず着用してください。
乾燥したフンの粉を吸い込むと、体調不良を引き起こす原因になりかねません。特にムクドリのフンには、真菌(カビの一種)が含まれていることがあり、「クリプトコッカス症」などの感染症を引き起こすリスクがあります。クリプトコッカス症を発症すると、肺炎のような症状や、重症化すると髄膜炎を引き起こすこともあります。免疫力の低い方や高齢者にとっては特に注意が必要です。
こうした感染症を防ぐためにも、必ずマスクを着用しましょう。
また、手袋を使うことで、フンに直接触れることによる皮膚からの感染を防ぐことができます。使い捨てのゴム手袋を使用し、作業後は、石鹸で手洗いを行ったうえで、アルコール消毒も行いましょう。
少し水に濡らす
乾燥したフンをそのまま掃除しようとすると、空気中にフンが舞い上がり、吸い込むことで感染症を引き起こすリスクがあります。
そのため、掃除の前にはまず水で軽く濡らし、ふやかしながら掃除するのが安全です。フンが落ちている場所が水で流せるのであれば、直接水で洗い流すのが良いでしょう。水で流せない場合でも、霧吹きなどで一度水を含ませましょう。
新聞紙などで拭き取る
フンを水で十分に湿らせて柔らかくしたら、新聞紙や使い捨ての布、キッチンペーパーなどを使って、丁寧に拭き取っていきます。このとき、フンを広げないよう、押し当てるようにして優しく取り除くのがポイントです。
拭き取った紙類や布は、ビニール袋に密閉して処分するようにしてください。そのままゴミ箱に捨てると、菌やニオイが広がる原因になります。使用した袋はしっかりと口を結び、地域のゴミ出しルールに従って処理しましょう。
除菌する
清掃後は、フンのあった場所をしっかり除菌しましょう。ムクドリのフンには、細菌や真菌(カビの一種)、寄生虫の卵などが含まれている可能性があり、肉眼では確認できない病原体が残っていることがあります。
除菌には、市販のアルコールスプレーや次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤を水で薄めたもの)が効果的です。特に、フンがこびりついていた部分や、その周囲までしっかりスプレーし、数分間放置してから拭き取ることで、より確実に菌を死滅させることができます。
また、使用した掃除道具(雑巾やブラシなど)は、可能であれば使い捨てにし、再利用する場合は熱湯や漂白剤で十分に消毒しましょう。作業が終わったら、最後にもう一度手洗いや手指の消毒を忘れずに行ってください。
ムクドリのフン被害の予防策

フンを掃除するだけでは、根本的な解決にはなりません。一度ムクドリに「居心地の良い場所」と認識されると、何度追い払っても同じ場所に戻ってきてしまう可能性があります。その結果、フン被害が再発し、掃除とストレスの繰り返しに悩まされることになりかねません。
こうしたフン被害を未然に防ぐためには、ムクドリが寄りつかない環境づくりをする必要があります。ポイントは、ムクドリに「ここは危険・居心地が悪い」と感じさせることです。そのためには、巣を作らせない・とまらせない・侵入させないといった視点での対策が大切です。
ここからは、今すぐ始められる具体的な予防策を3つ紹介します。どれも専門知識がなくても実践しやすい内容なので、ぜひ取り入れてみてください。
巣を作らせない
ムクドリによるフン被害を防ぐうえで、最も効果的なのが「巣を作らせないこと」です。巣を起点にどんどんムクドリが増えていき、フンの量や範囲も急激に拡大してしまいます。
特に、屋根の隙間や換気口、ベランダの天井のような、ムクドリが入り込めるすき間があると、あっという間に巣を作ってしまいます。巣を作らせない対策としては、以下のような方法が効果的です。
- パンチングメタル(穴があいた鉄板)や金網で通気口を塞ぐ
- 屋根裏や軒下に隙間があれば、コーキング剤などで封鎖する
- ベランダの室外機やダクトのすき間に、目の細かいネットを取り付ける
ただし、すでに巣が作られている場合には注意が必要です。ムクドリは「鳥獣保護管理法」により、卵やヒナがいる状態での巣の撤去が原則禁止されています。勝手に撤去すると法律違反になる可能性があるため、卵やヒナがいる場合は、市区町村や専門の駆除業者に相談しましょう。
ムクドリの巣の駆除方法や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
道具を使って追い払う
ムクドリはとても警戒心の強い鳥のため、道具を使って、ムクドリの視覚や聴覚を刺激することで追い払うことができます。以下のような方法は、家庭でも簡単に取り入れやすいです。
- 反射テープやCD
キラキラ光る素材は、ムクドリにとって不快な刺激になります。風で揺れることでランダムに光を反射し、「落ち着かない場所だ」と感じさせる効果があり、木の枝やベランダに吊るすだけで簡単に設置できます。
- 天敵の模型(カラス・タカなど)
ムクドリが警戒する猛禽類の模型を設置することで、「天敵が近くにいる」と錯覚させ、寄りつきにくくなります。
- 音響装置(超音波装置など)
超音波装置は、人間には聞こえにくい高周波の音を出し、ムクドリに不快感を与えます。また、カラスの鳴き声や鳥の悲鳴などを再生する装置も、ムクドリに警戒心を与える手段として効果的です。
ただし、ムクドリは音や光に慣れやすい鳥です。効果を継続させるには、設置場所を定期的に変えるなどの工夫が必要です。
道具を使ったムクドリ対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。
防鳥ネットやスパイクを設置して侵入を防ぐ
ムクドリの侵入を防ぐためには、ムクドリがとまりやすい場所を塞ぐ対策も効果的です。
例えば、ベランダの手すり部分に防鳥ネットを取り付けることで、ムクドリが中に入り込むのを防げます。さらに、電線や塀などムクドリがとまりやすい場所には、防鳥スパイクを設置することで、「ムクドリをとまらせない」環境を作ることが可能です。
防鳥スパイクとは、細い突起が一定間隔で並んでいる道具で、設置することで鳥が足場を確保できなくなります。見た目は鋭く見えるかもしれませんが、ムクドリにケガをさせることなく、「とまりにくくする」ことを目的とした安全な対策グッズです。
ただし、防鳥ネットを使う際には設置方法に注意が必要です。取り付けが甘いと、かえってムクドリに「外敵から守られる安全な場所」と認識され、ネット内に巣を作られてしまう可能性があります。
このように、やり方を間違えると逆効果になるケースもあるため、「自分で全部やるのは難しそう…」と感じた方は、専門業者に相談するのが安心で確実です。
参考:日本有害鳥獣駆除・防除管理協会「ムクドリを撃退する方法とは?自身でできる対策や業者依頼時の費用を解説!」
ムクドリ駆除はお任せください!
ムクドリのフン被害が深刻な場合や自力での対策が難しい場合は、ぜひ「害獣BUZZ」にご相談ください。害獣BUZZは、ムクドリをはじめとした鳥類・害獣の駆除を専門に行う害獣駆除のプロフェッショナルです。
経験豊富で専門知識を備えたスタッフが対応するため、安心して依頼することができます。害獣BUZZでは、現地調査から施工、アフターサービスまでをすべて自社で一貫して行っており、間に仲介業者を挟まないため、中間マージンなどの余計な費用がかかりません。
さらに、施工内容も現場の状況やムクドリの生息数、被害の程度に合わせて柔軟に対応できるため、効率的かつ無駄のない対策が可能です。
もちろん、すべての作業は鳥獣保護管理法をはじめとする法令に基づいて行われるため、法的なトラブルを心配する必要もありません。
害獣BUZZでは、ムクドリだけでなく、アライグマやネズミなどの害獣にも対応しており、侵入経路の封鎖から清掃、再発防止までを一貫してサポートしています。まずは無料相談から、お気軽にご相談ください。
まとめ
ムクドリのフンは、見た目やニオイの問題だけでなく、健康被害や建物の劣化を招くこともあります。フンの掃除には正しい手順が必要であり、マスクや手袋などの予防策も欠かせません。
ただし、最も重要なのは「フンを落とされない環境づくり」です。巣を作らせない、視覚・聴覚で威嚇する、とまり場を排除するといった予防策を講じることで、長期的な被害防止に繋がります。
自力での対策が難しいと感じたら、専門の駆除業者に依頼することも検討してみてください。
害獣BUZZでは、無料の現地調査を行っているため、ムクドリの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |