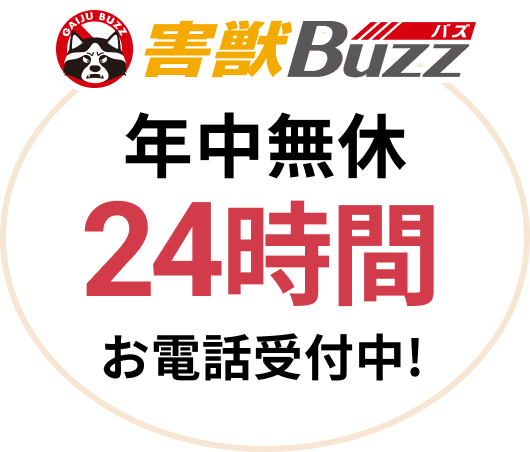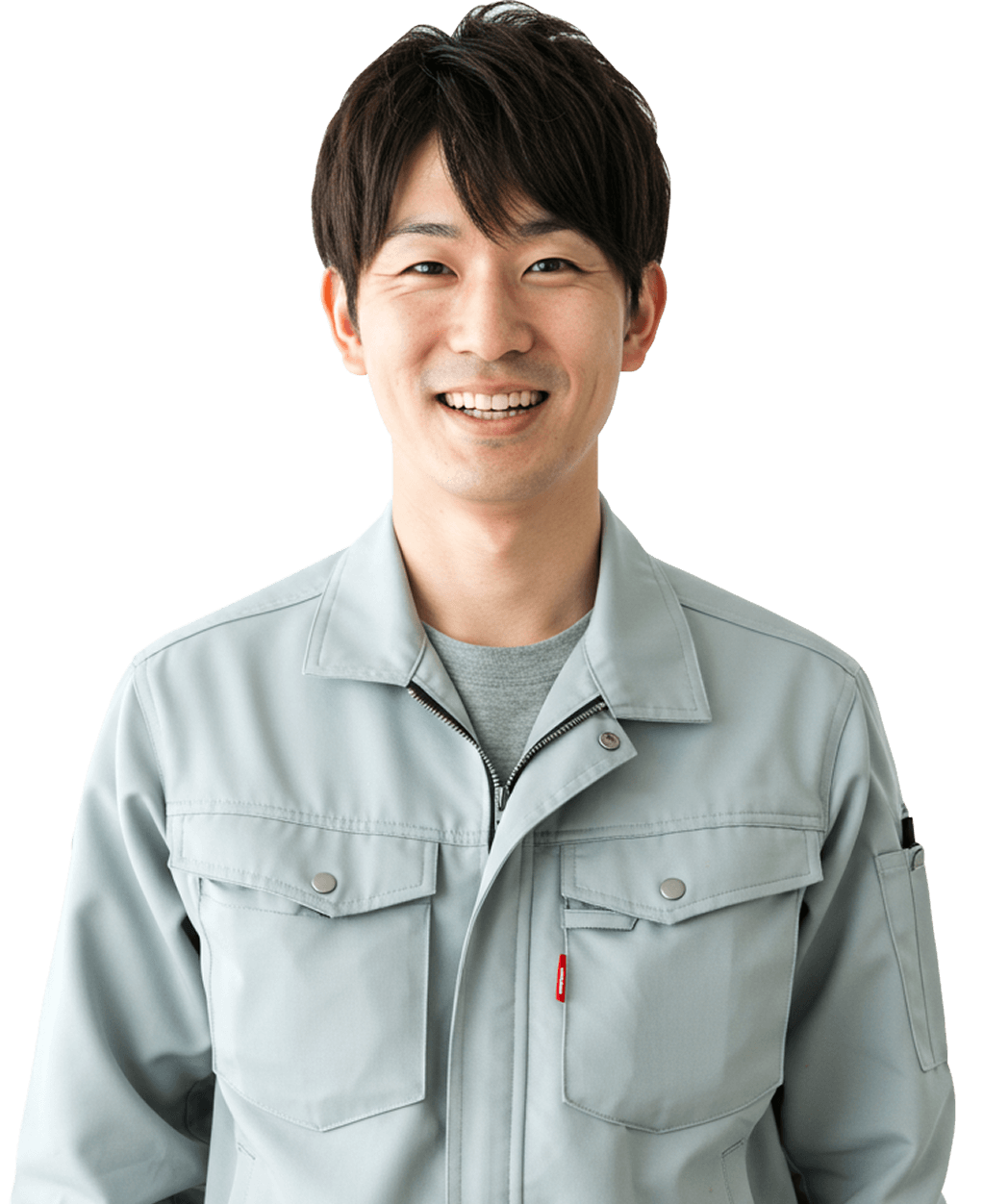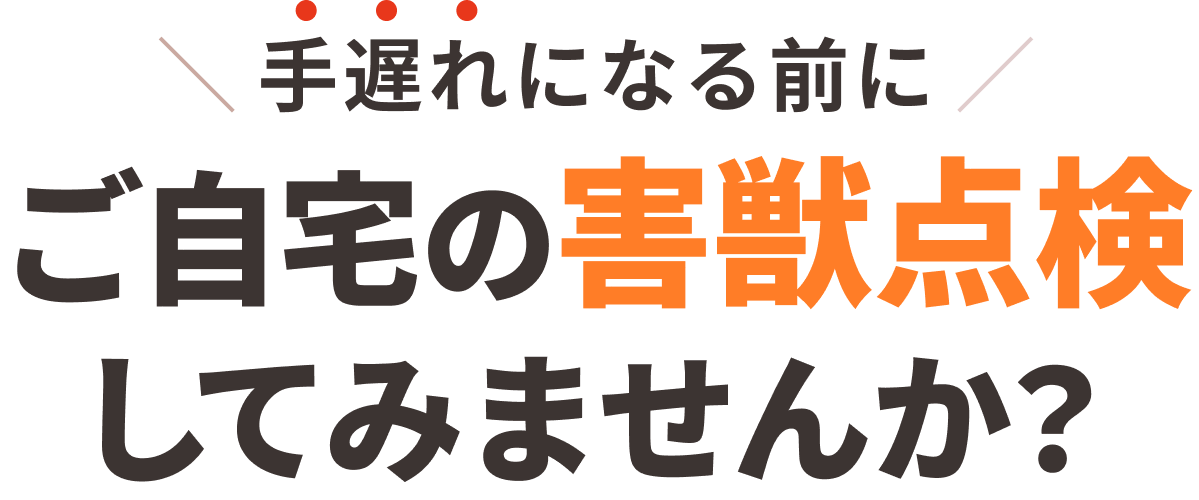アナグマを捕獲する方法と注意点を徹底解説

アナグマによる被害に悩まされている方は少なくありません。畑を荒らされたり、床下に住み着かれたりと、被害は多岐にわたります。そんなとき「捕獲して解決したい」と考えるのは自然なことですが、実はアナグマの捕獲には法律や手順、注意点が数多く存在します。
特にアナグマは「鳥獣保護管理法」により保護されており、許可なく捕獲することは違法です。また、アナグマは夜行性で警戒心が強く、素人が安全かつ確実に捕まえるのは困難です。
今回は、アナグマの捕獲を検討している方に向けて、以下の情報を徹底的にわかりやすく解説します。
- 実際の捕獲方法と使われる道具
- 捕獲前に確認すべき法律や手続き
- 捕獲後の対応や再発防止策
被害を最小限に抑え、法的トラブルを回避するためにも、まずは正しい情報を知ることが第一歩です。本記事で紹介する内容を参考に、安全かつ適切なアナグマ対策を進めていきましょう。
目次
アナグマを捕獲するなら箱わなが一般的

アナグマの捕獲には、箱わなの使用が最も一般的な方法です。
アナグマは夜行性で警戒心が強いため、捕獲には慎重な計画と適切な道具が必要です。中でも箱わなは、アナグマの通り道に設置しやすく仕掛けも単純なため、扱いやすさと効果のバランスが良い点が評価されています。
箱わなの種類
アナグマを効果的に捕獲するには、用途に適した箱わなを選ぶことが重要です。箱わなにはいくつかの種類があり、サイズや構造によって適性が異なります。
アナグマ捕獲には、強度とサイズに優れた中〜大型の箱わなを選ぶのがポイントです。
アナグマは体重が12~13kgと比較的大きく、力も強いため、小型動物用のわなでは破損するおそれがあります。誤って他の動物がかかるリスクを避けるためにも、構造や入り口サイズにも注意が必要です。
以下は、アナグマ捕獲で使用される代表的な箱わなの種類です。
| 種類 | 詳細 |
| 片扉式 | 入り口が片側のみのシンプルな構造。設置や管理が簡単。 |
| 両扉式 | 両端に入り口があり、通り抜け型。警戒心が強い動物に有効。 |
| 強化スチール製 | 鉄製で頑丈。大型動物にも耐えられる。 |
| 折りたたみ式 | 保管や運搬に便利。設置にはやや手間がかかる。 |
アナグマ捕獲に失敗しないためには、頑丈でサイズの合った片扉式または両扉式の箱わなを選ぶのがベストです。特に強化スチール製のものは、アナグマの力に耐えられるため、安全で確実な捕獲が期待できます。
設置場所
箱わなは、アナグマの通り道や出没場所を狙って設置することが重要です。アナグマは基本的に夜行性で、決まったルートで餌場と巣を往復します。そのため、アナグマの行動パターンを把握して実際に出没している場所に設置することで、捕獲率が大きく向上します。
具体的には、以下のような場所に箱わなを設置するのが効果的です。
- 畑や庭先
- 穴や掘り返した跡の近く
- 塀の隙間・獣道
- 物陰・茂みの脇
エサ選び
アナグマの捕獲において、エサ選びも成功率を大きく左右するポイントです。箱わなを設置しても、アナグマの好むエサでなければ警戒されてしまい、わなに近づいてもらえません。
アナグマの嗅覚を刺激する、甘くてニオイの強い以下のようなエサを選びましょう。
- バナナ
- リンゴ
- コーン缶詰
- 市販の獣専用の誘引剤
アナグマは夜行性で、視覚よりも嗅覚に頼って餌を探します。特に果物や甘いものが好物で、ニオイで誘導されます。逆にニオイが弱いものや警戒心を与えるエサは、逆効果になりかねません。
設置後もエサの鮮度や配置をチェックし、雨などで効果が薄れないよう注意しましょう。
アナグマを捕獲する際の注意点

アナグマの被害に困っている方にとって、捕獲は有効な手段のひとつです。ただし、捕獲には守るべきルールや注意点があり、間違った対応はトラブルや法令違反につながる可能性があります。
アナグマを捕獲する際、特に注意しておきたい点は、以下の3つです。
- 再発対策を行う
- 法律を遵守する
- 直接触れない
それぞれの注意点を順番に詳しく解説します。
再発対策を行う
アナグマを捕獲して一時的に被害が収まっても、根本的な対策を怠れば再び侵入されてしまうおそれがあります。アナグマの再侵入を防ぐには、捕獲後すぐに物理的・環境的な再発対策を講じる必要があります。
アナグマは帰巣本能が強く、過去に居ついた場所に再び戻ってこようとする習性があります。捕獲で一度は姿を消しても、巣やエサのニオイが残っていれば、別の個体や元のアナグマが戻ってくる可能性が高いです。
アナグマの再侵入を防ぐためには、次のような対策を組み合わせることが効果的です。
- 侵入口の遮断
- 巣の撤去・清掃
- エサとなるものの撤去
- 忌避剤・ライトの活用
- 柵・ネットの設置
捕獲は、アナグマ対策の第一歩にすぎません。再発を防ぐには、環境を整え、侵入経路や誘惑を断つことが不可欠です。
法律を遵守する
アナグマは、鳥獣保護管理法により保護されている野生動物です。この法律は、鳥獣の乱獲や不適切な扱いから自然環境や生態系を守る目的で定められています。たとえ人に被害を与える場合であっても、アナグマの捕獲には原則として自治体の許可が必要です。
アナグマの捕獲にあたっては、次のような流れで自治体に申請対応を行います。
- 地元の市区町村役場または環境課にアナグマ被害を相談する
- 鳥獣保護管理法に基づく「有害鳥獣捕獲許可申請書」などを提出する
- 期間、場所、方法などが記載された捕獲許可証が交付される
- 指定の方法で捕獲し、結果(捕獲数や場所など)を報告する
確実に安心して被害を防ぐためにも、自治体への相談と正しい手続きが第一歩です。
ご自身での対応が不安な場合は、害獣駆除業者に相談するのもオススメです。法律に基づいた適正な対応をしてくれるため、安心して任せられます。
直接触れない
アナグマを捕獲しても、絶対に直接触れてはいけません。手袋・器具などを使って安全に取り扱う必要があります。
アナグマは、凶暴である上に病原菌を持っている可能性がある野生動物です。直接触れると、以下のようなリスクがあります。
- 噛まれる・引っかかれる
- 感染症を移される
アナグマを捕獲した際は、以下のような安全対策を必ず行いましょう。
- 厚手の革手袋や作業用グローブを装着し、素手での接触を避ける
- 長袖や長ズボンで肌の露出を避け、引っかかれたり噛まれたりするリスクを減らす
- 長靴で足元も防御し、地面に潜む病原菌や排泄物との接触を防ぐ
- 箱わなのまま移動させ、アナグマには直接触れない
- 自分で対処が難しい場合、すぐに駆除業者や自治体に連絡する
安全第一を忘れず、適切な方法で被害対策を進めましょう。
アナグマを個人で捕獲するのはオススメできない

アナグマによる被害を受けて、「自分で何とか捕まえたい」と考える方も多いかもしれません。しかし、アナグマを個人で捕獲するのは、基本的にオススメできません。理由は明確で、法律上の規制や安全面のリスク、効果の不確実性などの懸念点があるためです。
無理な自己対応は、かえって事態を悪化させかねません。トラブルを防ぐためにも、まずは専門業者や自治体に相談し、正しい手順で対応することが重要です。
アナグマ駆除はお任せください!
アナグマを自力で罠にかけて捕獲することは可能ですが、非常に手間がかかり、危険を伴います。許可の取得、罠の設置や回収、捕獲後の対応まで、慎重に進めなければなりません。
特に注意が必要なのは、罠にかかったアナグマの取り扱いです。アナグマは非常に攻撃的になることがあり、噛みつきや引っかきによって怪我を負ったり、感染症を媒介されたりするリスクがあります。
そのため、アナグマ駆除は専門の業者に依頼するのが安全で確実です。
私たち「害獣BUZZ」は、アナグマを含むさまざまな害獣の駆除を専門とする業者です。豊富な経験と知識をもとに、お客様の状況に合わせた最適な駆除プランをご提案いたします。
罠の設置から回収、捕獲後の処理、再発防止や除菌まで、すべての作業を法令に基づいて丁寧に対応いたします。
駆除して終わりではなく、快適で安心できる暮らしの実現をお手伝いするパートナーとして、末長くサポートいたします。現地調査とお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
アナグマによる被害は、農作物の食い荒らしや住宅周辺の掘り返し、騒音・悪臭といった生活トラブルを引き起こします。そうした被害を解決するために「捕獲」は有効な手段のひとつですが、法律や安全面の配慮が欠かせません。
「一刻も早く何とかしたい」と思うあまり、自己判断でアナグマを捕獲しようとするのは非常に危険です。まずはお住まいの自治体や、鳥獣被害対策に詳しい専門業者へ相談し、合法的で安全な方法での対応を進めましょう。
害獣BUZZでは無料の現地調査を実施しておりますので、アナグマのような動物による被害でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |