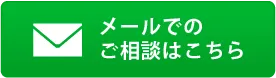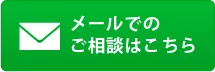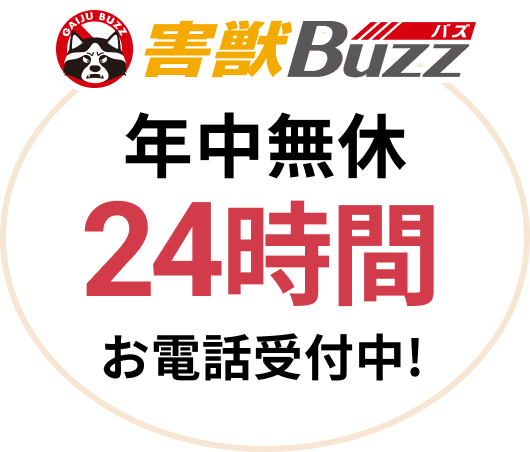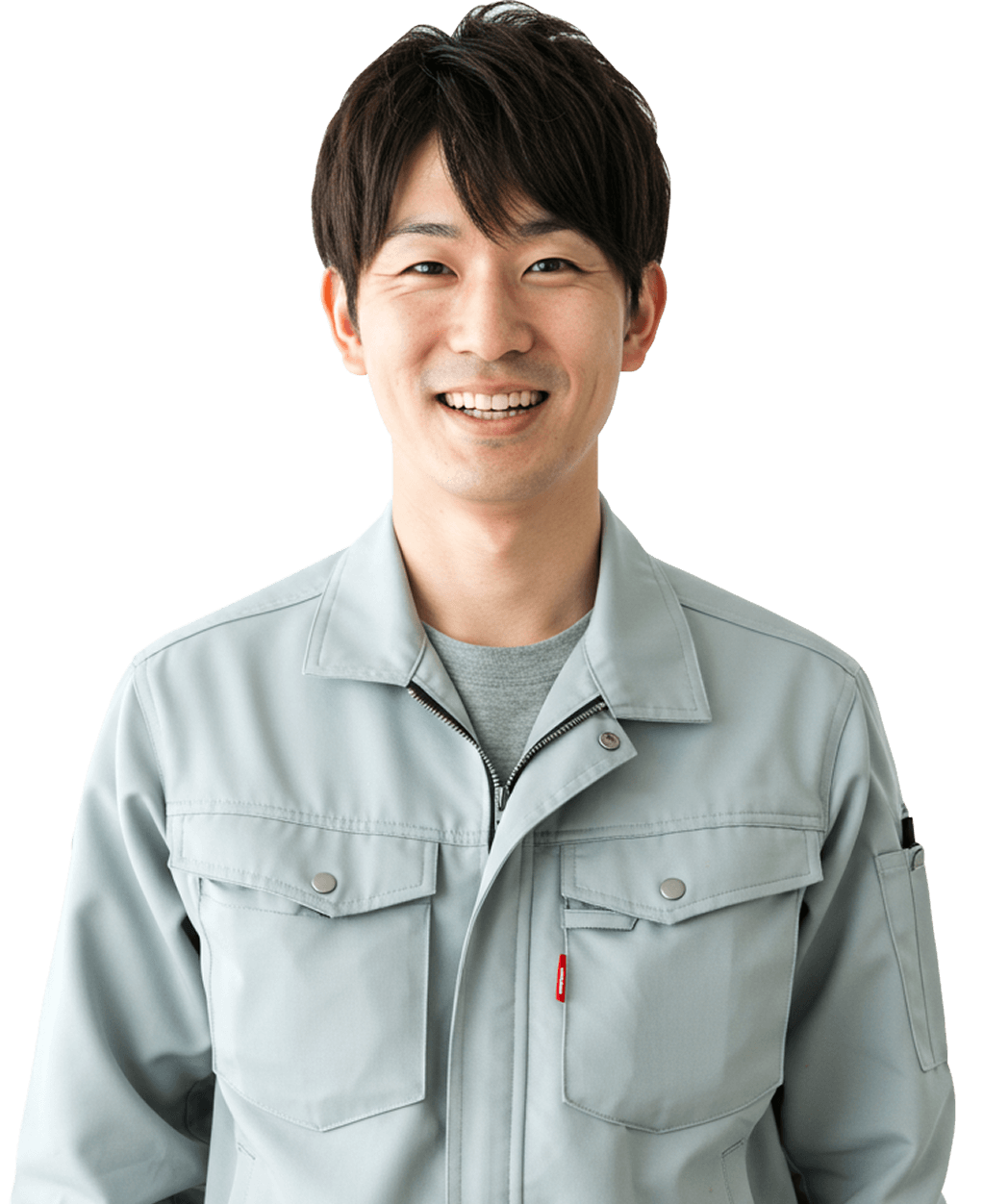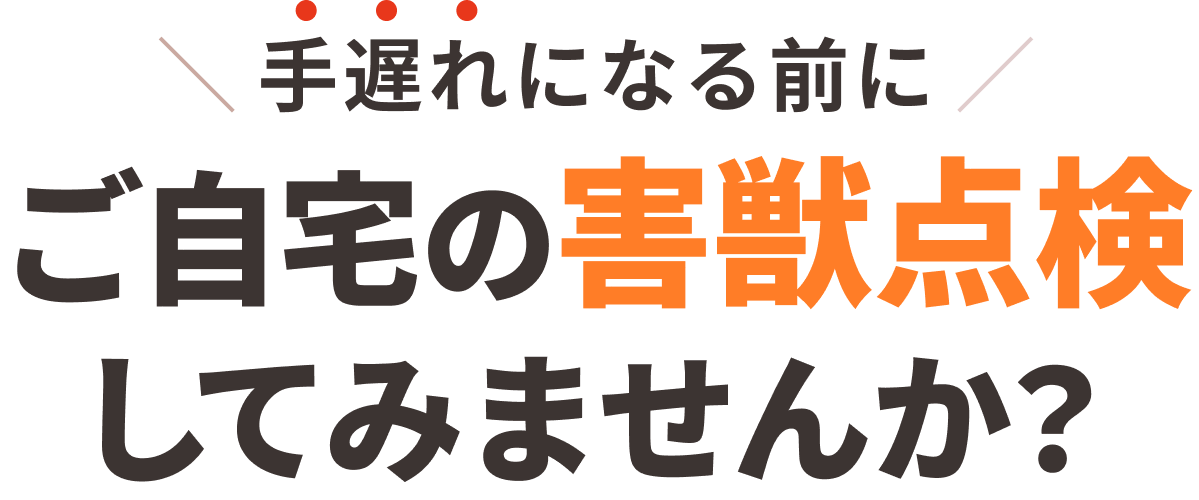コウモリを寄せ付けない方法は主に3つ!超音波や光の効果についても解説

「軒下にコウモリが来ていて不安」「フンが落ち始めて迷惑」とお困りではないでしょうか。
市街地に住みつくコウモリは、わずか1〜2cmの隙間から家屋に入り込み、健康被害や衛生環境の悪化、建物の損傷をもたらします。放置しても自然にいなくなるとは限らず、むしろ被害が広がるケースが少なくありません。
本記事では、今日からできるコウモリを寄せ付けない環境づくりの具体策を、忌避剤や超音波や光を使用する注意点も交えて解説します。また、侵入させない対策と本格的な駆除はプロに依頼するのがおすすめな理由も紹介します。
正しい知識と手順を押さえ、安全な住環境を守る第一歩を踏み出しましょう。
目次
コウモリを寄せ付けない環境づくり

コウモリは居心地のよい場所だと判断した家に長く留まります。つまり、環境の工夫次第で近寄りにくい家に変えることが可能です。
ここでは、コウモリを寄せ付けない3つの方法を解説します。日常の中でできる小さな対策から始め、被害を未然に防ぎましょう。
コウモリが嫌うニオイ・忌避剤を設置する
コウモリはハッカなどの強いニオイを嫌うため、忌避剤による対策は取り入れやすい方法です。コウモリ用の忌避剤には主に次の3種類があります。
- スプレータイプ:シャッター内や換気口などの狭い場所に向いており、即効性がある
- くん煙タイプ:屋根裏や物置などの広い密閉空間に向いており、煙で一時的に追い出せる
- ジェルタイプ:置くだけで使用可能だが、コウモリが絡まり死んでしまう恐れがあり推奨されない
コウモリは鳥獣保護法で保護されており、無許可での殺傷・捕獲は罰則の対象です。忌避剤は追い出す目的に限定して使いましょう。
コウモリに有効な忌避剤については、以下の記事で解説しています。
水たまりを作らない
コウモリは直接水に集まるのではなく、水場に発生する蚊などの虫を求めて寄り付きます。家の周りに水たまりや水が残りやすい場所があると、結果的にコウモリを呼び寄せる原因になります。
地面が凹んで水が残る場所は砂利や土で均し、バケツやジョウロ・植木鉢の受け皿などに水が残っていないかも定期的に確認しましょう。
小さな水場を減らすだけでも、餌となる虫の発生を抑え、コウモリが近寄りにくい環境づくりにつながります。
定期的に雨戸やシャッターを開閉する
コウモリは暗くて静かで、人の出入りが少ない場所をねぐらに選びます。雨戸やシャッターは長期間閉めっぱなしにすると内部が暗く静かな空間になり、住み着きやすくなります。
定期的に開閉して光と音を入れるだけでも、コウモリにとって好ましくない環境にすることが可能です。
特に長期不在の前後や季節の変わり目は意識的に開閉し、習慣化すれば再発防止にもつながります。
コウモリ対策として超音波や光は過信NG

コウモリ対策として「超音波機器で近寄らなくなる」「ライトを当てれば逃げる」と思われがちですが、どちらも効果は一時的なものにとどまるケースが多く過信は禁物です。
ここでは効果が一時的になる理由と、使用する場合の正しい付き合い方を解説します。
超音波の効果は限定的
超音波機器は、コウモリの聴覚に刺激を与えて一時的に近寄りにくくする効果が期待できます。
ただし、コウモリは自ら発する超音波の周波数を変化させて環境に順応するため、時間が経つと慣れて戻ってくる例が多く、根本的な解決にはなりません。
また、壁や柱などの障害物があると音が減衰し、届きにくい場所ができてしまうことも問題です。
補助的手段として用いるにとどめ、過信しないことが重要です。
光も限定的だが、使用するならLEDを推奨
光にはコウモリを驚かせて一時的に離れさせる効果があります。
ただし、コウモリは視力が弱く明暗程度しか判断できないため、すぐに環境に慣れて再び寄り付きやすくなります。
光を使う場合は、蛍光灯ではなくLEDライトがおすすめです。蛍光灯は虫を引き寄せ、結果的にコウモリの餌場をつくってしまうため逆効果になる場合があります。一方、LEDは虫が寄り付きにくく、コウモリが近寄るリスクを抑えられます。
いずれにしても光は補助的な対策であるため、他の対策と併用して使う前提で検討しましょう。
コウモリを侵入させないための対策も必要

コウモリを外に寄せ付けない対策だけでは十分とはいえません。
万が一住み着かれた場合、外に寄り付いているよりも、フン害・悪臭・ダニの発生などの被害が一気に拡大するためです。
コウモリ対策には、近寄らせないと同時に侵入させない備えを並行して行いましょう。
コウモリが侵入した場合の被害
コウモリが家屋内に住み着いた状態を放置すると、被害は外にいるときよりも格段に深刻化します。
特に健康被害は看過できません。コウモリの体には多くのノミ・ダニが寄生しており、人に移ると皮膚炎やアレルギー症状を引き起こします。
さらに、フンには病原体が含まれており、乾燥して舞い上がった粉じんを吸い込むことで感染症を発症するリスクが指摘されています。以下は、コウモリによる代表的な感染症の例です。
- ヒストプラスマ症:フンに含まれる真菌(ヒストプラズマ)を吸い込んで感染し、発熱・咳・倦怠感など肺炎のような症状の他、免疫が弱い人では髄膜炎など重症化する場合がある
- サルモネラ感染症:フンや尿を介して感染し、下痢・腹痛・発熱など食中毒の症状が現れる
参考:動物由来感染症ハンドブック2018
ヒストプラスマ症
サルモネラ感染症
感染症以外にも、被害は日常生活に影響します。
コウモリのフン尿は強いアンモニア臭を発し、悪臭による衛生環境の悪化だけでなく、尿に含まれる酸性成分が木材や断熱材を劣化させ、天井にシミが出るなど建物自体の損傷にもつながります。
また、夜間の羽音や鳴き声で睡眠障害に悩まされる方も珍しくありません。
さらに、放置すると繁殖によって個体数が増え、被害は加速度的に拡大していきます。
コウモリの侵入が疑われた場合は、被害が拡大する前に早めの対策に着手しましょう。
コウモリによる健康被害は、以下の記事で解説しています。
1〜2cm程度の隙間から侵入してくることも
目立つ穴や破損が見当たらない家でも油断はできません。
コウモリは羽を折りたたんで体を細くできるため、わずか1〜2cm程度の隙間からでも容易に侵入します。換気口、外壁と配管の隙間、屋根の板金の合わせ目など、気づきにくい箇所が侵入口になりがちです。
「小さいから大丈夫」と放置するほど被害が拡大するため、微細な隙間も含めて徹底的に塞ぐ必要があります。
コウモリの侵入経路については、以下の記事で解説しています。
隙間を塞ぐ方法
侵入を防ぐには、見つけた隙間を素材に合わせて確実に塞ぐことが重要です。
1〜2cm程度ならシーリング材やパテで充填し、通気口や配管まわりなど常に開口が必要な場所はステンレス製の金網や防虫ネットで覆います。
封鎖作業は、コウモリが外に出ている夕暮れ以降に行うのが基本です。中に残したまま塞いでしまうと室内に回り込む危険があり、再発被害のもとになるため注意が必要です。
本格的な対策はプロへ依頼するのがおすすめ

コウモリ対策は自力でも始められますが、確実性と安全性を考えると専門業者への依頼が現実的です。
侵入口は1〜2cmの亀裂や換気口の奥など、人の目では見落としやすい場所に潜んでいます。全ての隙間を見つけるのは難易度が高いうえに、封鎖作業は屋根裏・軒下など高所や閉所が多く、落下や転倒による怪我のリスクが否定できません。
また、フンには病原体やダニが含まれるため、防護具の着用や徹底した除菌を行わなければ、感染のリスクがあります。
プロの業者であれば生態・構造を踏まえて適切に追い出しと再発防止まで一括対応でき、安心して任せられるでしょう。
コウモリ駆除は害獣BUZZにお任せください!

コウモリ被害を根本から解決するには、一時的に追い出すだけでなく、侵入経路を徹底封鎖して再発を防ぐことが不可欠です。
しかしコウモリは鳥獣保護法の対象動物であり、許可なく捕獲・殺傷をすれば罰則の対象となります。自己判断での対応は難しく、結果的に被害を長引かせてしまうケースも少なくありません。
害獣BUZZでは現地調査・見積もりを無料で実施し、専門スタッフが状況に応じた最適な対策をご提案します。
法律を守りながら、安全かつ確実に被害を解決できますので、費用や施工内容に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
コウモリは、屋根裏や換気口など狭い隙間から家屋に侵入し、そのまま住み着くことがあります。放置すれば、健康被害や衛生環境の悪化、建物の損傷などの被害につながるおそれもあります。
被害の拡大を防ぐには、日頃から寄せ付けない・侵入させない対策が必要です。
ご家庭でも忌避剤の活用やLEDライトの導入、隙間の封鎖などで一定の効果は期待できますが、必ずしも完全に防げるとは限りません。
不安がある場合や早期に解決したい場合は、専門業者への依頼が最も確実です。
「近くでコウモリを見かけて心配」「早く対処したい」という方は、ぜひ害獣BUZZまでご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |