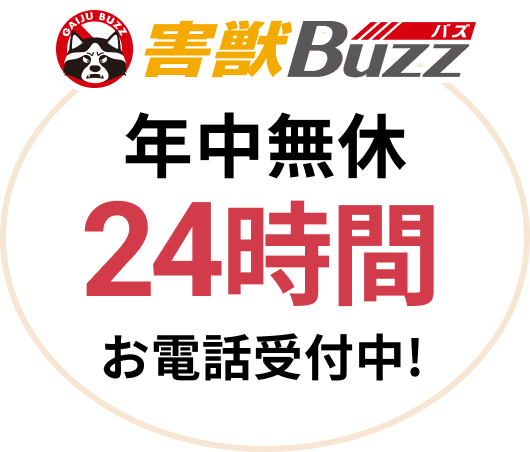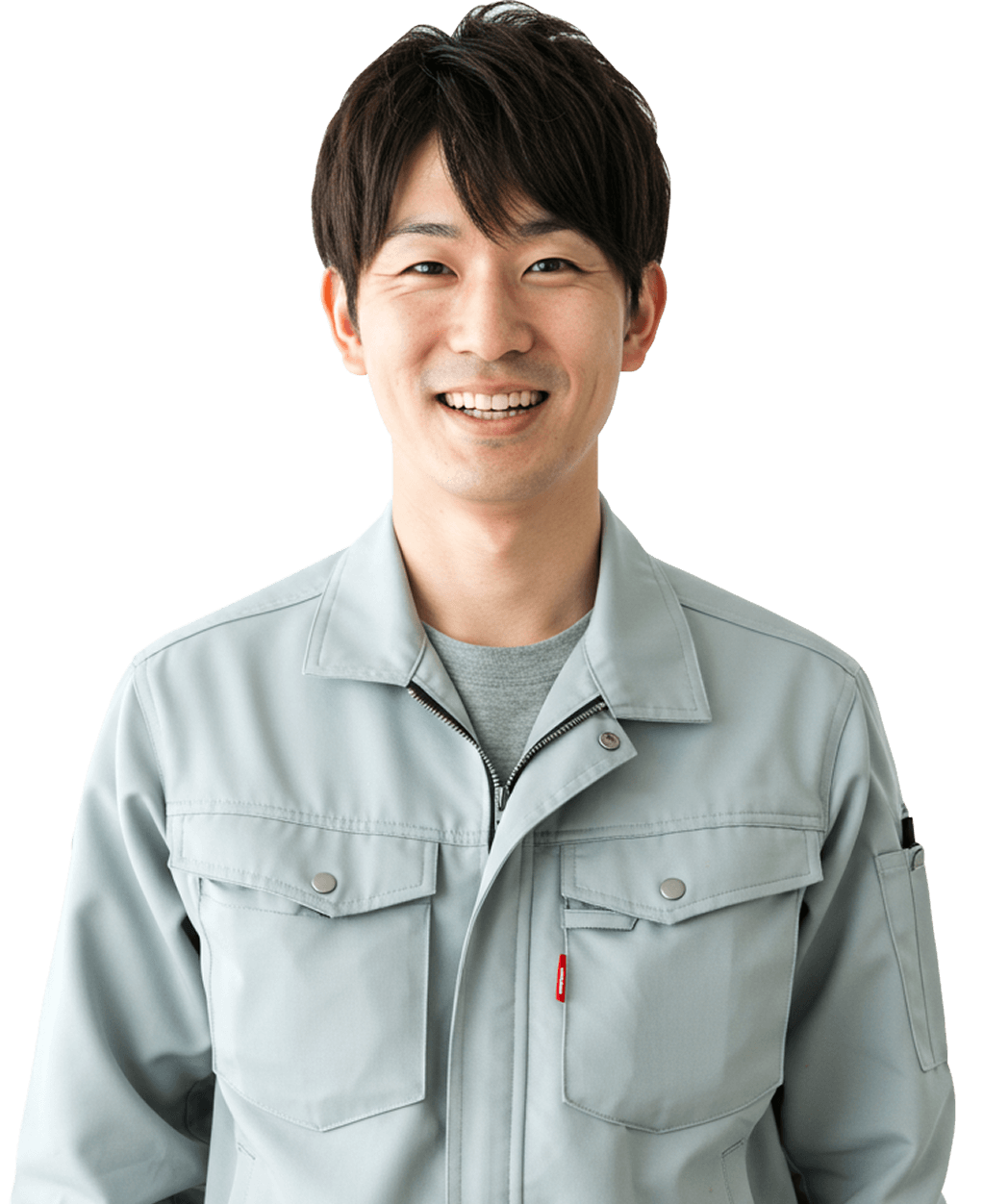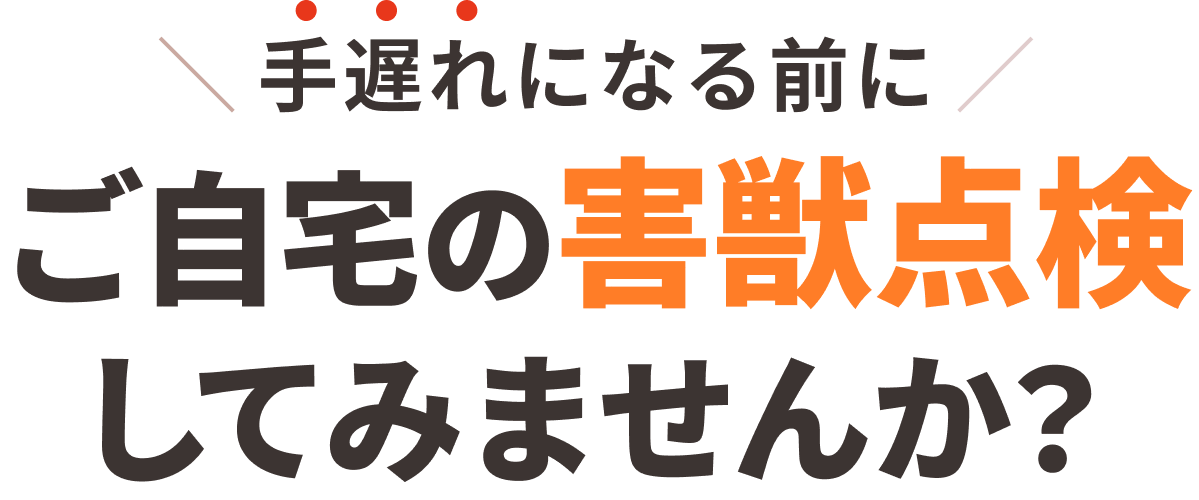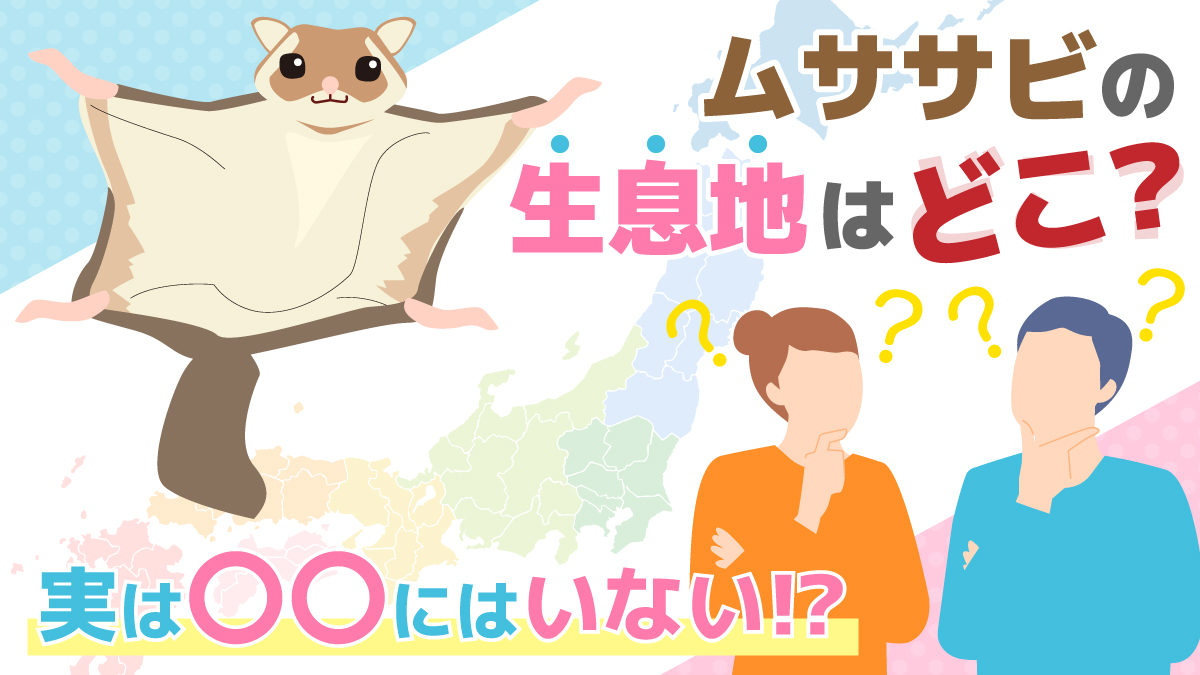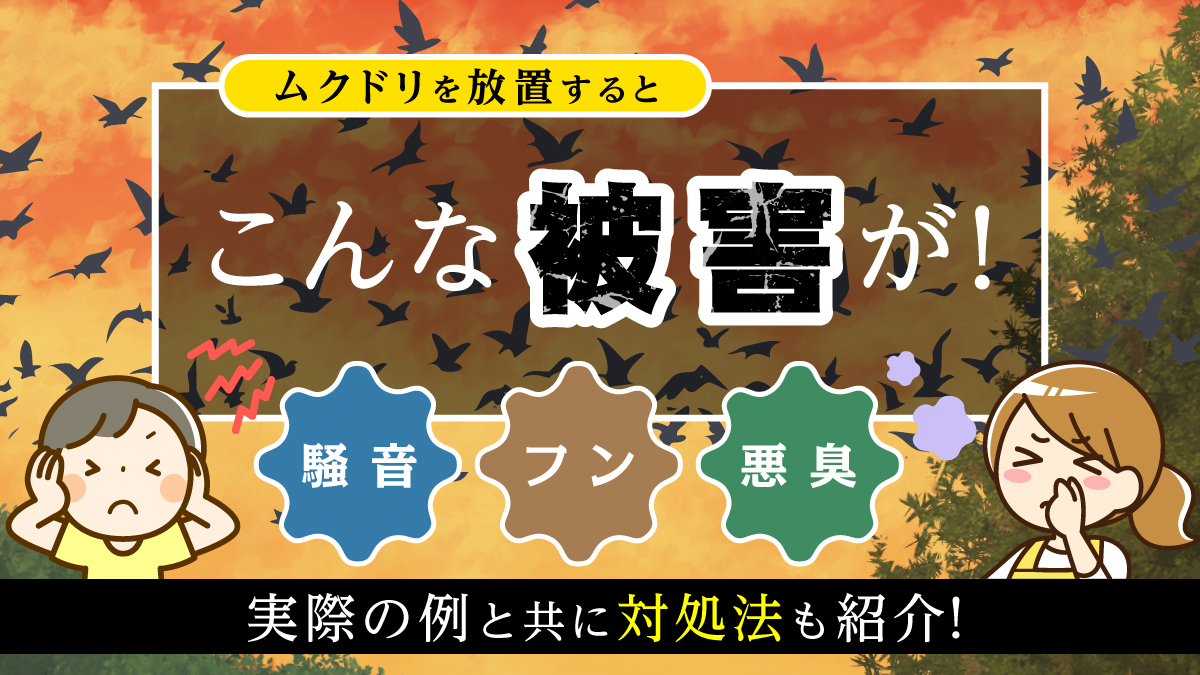アナグマの嫌いなものは何?駆除への活用方法も伝授!

「アナグマに庭を荒らされたり、物置の下に巣を作られた…」とアナグマによる被害に悩んでいませんか?アナグマは見た目こそ愛らしいものの、非常に警戒心が強く、駆除が難しい動物です。
本記事では、アナグマが嫌いなものとアナグマの効果的な駆除方法を詳しく解説します。自力での対策はもちろん、専門業者に依頼すべきタイミングや注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
アナグマが嫌いなものとは?

アナグマは基本的に臆病な動物で、人の生活圏に現れる場合でも、慎重に行動しています。そのため、特定の刺激に対して敏感に反応し、嫌がって逃げる習性があります。この習性を利用すれば、効果的なアナグマ対策が可能です。
まずは、ニオイ・音・光といった観点から、アナグマの嫌いなものを解説していきしょう。
ニオイ
アナグマは嗅覚が非常に発達しています。そのため、以下のようなニオイには一定の効果があります。
- 木酢液
- ミント
- ハッカ
ただし、明確に効果が保証されているわけではありません。あくまで「手軽に試してみよう」という気持ちで、忌避剤やスプレーとして利用するのがよいでしょう。
また、使用する場所を定期的に変えることで、アナグマにとって居心地の悪い環境を継続的に作り出すことができます。
音
アナグマは聴覚も敏感です。特に、以下のような予測不能な大きい音に驚きやすい傾向があります。
- 人間の声
- 金属音
- 風鈴の音
- 超音波機器の高周波
ただし、音による対策も個体差や環境により効果にムラがあるため、効果が保証されている訳ではありません。
音による対策は、夜間の静かな時間帯に音が響くように工夫することで、より高い忌避効果を期待できます。
光
夜行性であるアナグマにとって、以下のような明るい光も不快な刺激となります。
- センサーライト
- 点滅ライト
- 強力な懐中電灯
しかし、アナグマが光に慣れてしまう可能性もあります。そのため、ニオイや音と同様、「対策の一つとして加えておく」くらいの気持ちで、他の方法と組み合わせると効果的です。
また、照明機器は定期的に設置場所や向きを変えると、アナグマへの刺激が維持しやすくなります。
参考:農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル【総合対策編】」
アナグマが嫌いなものを活用した駆除方法
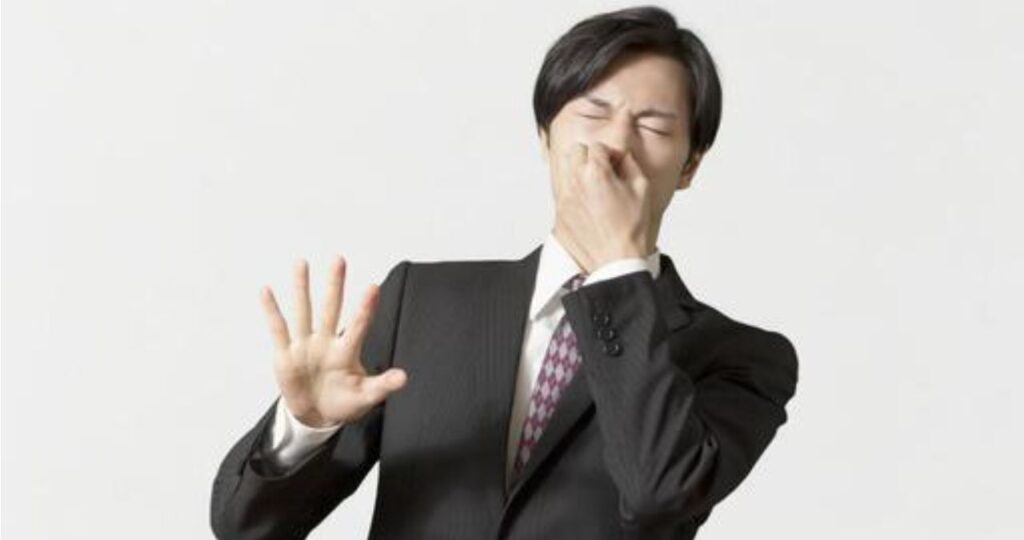
アナグマによる被害を防ぐには、アナグマの嫌いなものを活用する以下の3つの方法が効果的です。
- 嫌いなニオイで寄せ付けない
- 大きな音で驚かせる
- 強い光で驚かせる
家庭でも始めやすく、比較的手軽な対策のため、まずは一度試してみてください。
また、1つの対策だけでなく、3つの対策を組み合わせて実践するとより効果的です。ここからは、上記3つの対策について順番に詳しく解説します。
嫌いなニオイで寄せ付けない
アナグマを駆除するためには、「嫌いなニオイ」を活用する方法が有効です。アナグマが嫌いなニオイの忌避剤を散布することで、アナグマが近寄らなくなり、侵入を防ぐことができます。具体的には、以下の方法が効果的です。
- 市販の害獣忌避剤(動物や虫を近づけないために使う薬剤)を散布する
- 薄めた木酢液(木材を炭にする際に発生する煙を冷やして液体にしたもの)を散布する
- ニンニク・唐辛子を含んだ粉末やエキスを散布する
散布する際は、アナグマの通り道や侵入経路になりやすい場所に散布することがポイントです。
| 散布場所 | 効果・理由 |
| 建物の基礎回り | 床下や通気口など、アナグマが潜り込みやすい場所を遠ざける |
| 物置・倉庫の裏や下 | 暗くて静かで暖かい、アナグマが巣にしやすい環境への侵入を防ぐ |
| 庭や畑の周囲 | 食べ物を求めて侵入してくるアナグマの侵入口をブロックする |
| フェンスの下や隙間 | アナグマは地面を掘って侵入するため、通り道に匂いをつけて防止する |
| 動物の足跡のある場所 | アナグマの「通い道」を断つ。同じルートを繰り返し使う習性を逆手にとる |
また、数日ごとに何度か散布し、ニオイが持続するように工夫することも大切です。天候によって効果が薄れる場合もあるため、雨が降った後などには早めの再処置を心掛けましょう。
大きな音で驚かせる
アナグマだけでなく、野生動物は突然の音に驚いて逃げ出す習性があります。そのため、大きな音で驚かせる方法もアナグマを追い払うために有効です。具体的には、以下の方法が効果的です。
- 人感センサー付きの警告音機器を設置する
- 空き缶や鈴を吊るして、揺れるたびに音が鳴るようにする
- 録音した犬の鳴き声や金属音をタイマーで再生する
ただし、同じ音を繰り返すだけではアナグマが慣れてしまうため、音の種類や間隔を変える工夫が必要です。
強い光で驚かせる
強い光で驚かせる方法もアナグマの駆除に一定の効果があります。具体的には、以下の方法が効果的です。
- 夜間にセンサーライトを設置する
- LEDライトを庭や侵入経路に点灯させる
- ストロボ機能付きの防犯ライトを使用する
ライトの位置や照射角度を定期的に変えることで、アナグマの警戒心が維持しやすくなります。照明の点滅パターンを変更するなどの工夫をしてみましょう。
参考:日本有害鳥獣駆除・防除管理協会「アナグマってどんな動物?見つけたらどうすべき?アナグマの生態や害獣被害を解説」
完全に駆除するなら侵入経路の封鎖が必須

ニオイや音、光などで一時的にアナグマを遠ざけることは可能ですが、これらの方法だけでは根本的な解決には繋がりません。
再発を防ぎ、確実に被害を止めるには、アナグマの侵入経路を徹底的に塞ぐ必要があります。
【屋外】電気柵やフェンス
アナグマの畑や庭への侵入を防ぐには、電気柵やフェンスを活用した以下の対策が有効です。
- 電気柵を張り巡らせる(低い位置に2~3段)
- 金網やフェンスを地中30cm程度まで埋め込む
- 土嚢などで掘り返しを防ぐ
電気柵は、ホームセンターや農業資材専門店などで購入できます。市販品の多くはセット販売されており、柵の高さは60〜90cm、支柱の間隔は1〜2mが目安です。アナグマ対策としては、地面すれすれから2〜3段に分けて設置する方法が効果的です。
金網やフェンスを使う場合は、アナグマの掘削対策として垂直に設置するだけでなく、地中にL字型に折り曲げて30cm以上埋め込むのがポイントです。これにより、アナグマが下から掘って侵入するのを防ぐことができます。
アナグマは地中を掘る能力が高いため、地面の対策が重要です。簡易なフェンスでは突破される恐れがあるため、施工時は強度と深さに注意して設置しましょう。
【屋内】パンチングメタルやコーキング剤
物置や床下など、すでにアナグマに侵入されている場合には以下の対策が効果的です。
- 通気口や隙間にパンチングメタルを設置する
- 小さな隙間をシリコンやコーキング剤で封鎖する
- 排水管や配線穴にも目張りをする
パンチングメタルとは、小さな穴が無数に開いた金属板のことで、通気性を保ちながら動物の侵入を防ぐことができる素材です。主に通気口や排気口のカバーとして使われます。
一方、コーキング剤とは、建物のすき間や接合部を密閉するために使うペースト状の充填材で、防水・防虫・防音などの目的にも活用されています。アナグマの侵入を防ぐには、壁の隙間や配管まわりなどに塗り込んで物理的に遮断することができます。
また、封鎖作業をする際は、アナグマが中にいないことを必ず確認してください。内部に閉じ込めてしまうと、さらなる被害や法的な問題に繋がる恐れがあります。
参考:日本有害害獣駆除・防除管理協会「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】」
アナグマを駆除する際の注意点

アナグマ対策には法的な制限があるため、正しい知識のもとで実施する必要があります。ここからは、以下3点のアナグマを駆除する際の注意点を詳しく解説します。
- 自治体では駆除してくれない
- 捕獲には許可が必要
- 小さな隙間でも侵入してくる
自治体では駆除してくれない
アナグマの被害があっても、自治体が駆除してくれるケースはほとんどありません。
そのため、基本的には個人や専門業者による対応が必要です。
まずは自治体の役所や環境担当課に相談し、対応可能な範囲を確認しておきましょう。
「庭や畑などで見たことのないフンを見つけたけれど、アナグマかどうかよくわからない…」という場合は、下記記事でアナグマのフンについて詳しく解説しています。
捕獲には許可が必要
アナグマは鳥獣保護管理法により保護されているため、以下2点に留意する必要があります。
- 捕獲には自治体の許可が必要
- 無許可での捕獲や殺処分は法律違反
無許可でアナグマを捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
被害が深刻な場合でも、自分で駆除はせずに、まずは自治体や専門業者に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。適切な手続きを経て、専門業者に依頼することで、法令を順守した安全な駆除が可能となります。
被害を最小限に抑えるためにも、自己判断での駆除は避け、専門家の助言を仰ぐようにしましょう。
小さな隙間でも侵入してくる
アナグマは、わずか3cm程度の隙間からでも侵入することができます。そのため、「こんなに小さい隙間でも?」という場所から侵入されてしまうケースが多々あります。
また、すべての隙間を自分で見つけるのは非常に難しく、専門的な知識や経験が必要です。そのため、専門業者への相談が、被害を食い止めるためには確実な方法です。
アナグマを捕獲する際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
アナグマ駆除はお任せください!
自分で対策をしても解決しない場合や、再発を繰り返す場合は、専門の駆除業者に依頼するのが最も安心です。専門業者では、以下のような対応が可能です。
- 侵入経路の徹底調査
- 再発防止の対策
- 法令を順守した捕獲・駆除
業者選びでお悩みの方は、ぜひ「害獣BUZZ」にご相談ください。アナグマをはじめとする様々な害獣に対応しており、侵入経路の封鎖から清掃、再発防止までを一貫してお手伝いいたします。
まとめ
アナグマが嫌いなものには、強いニオイ・大きな音・強い光があります。3つを組み合わせた対策を講じることで、ある程度の忌避効果が期待できます。
ただし、根本的な解決には、侵入経路を封鎖する物理的対策が必要不可欠です。
さらに、アナグマは法律で保護されている動物であるため、無許可で駆除はできません。被害が深刻な場合は、速やかに自治体や専門業者へ相談しましょう。
害獣BUZZでは、無料の現地調査を行っているため、アナグマの被害でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |