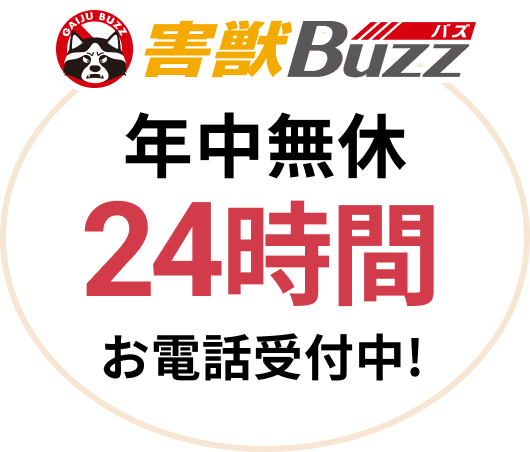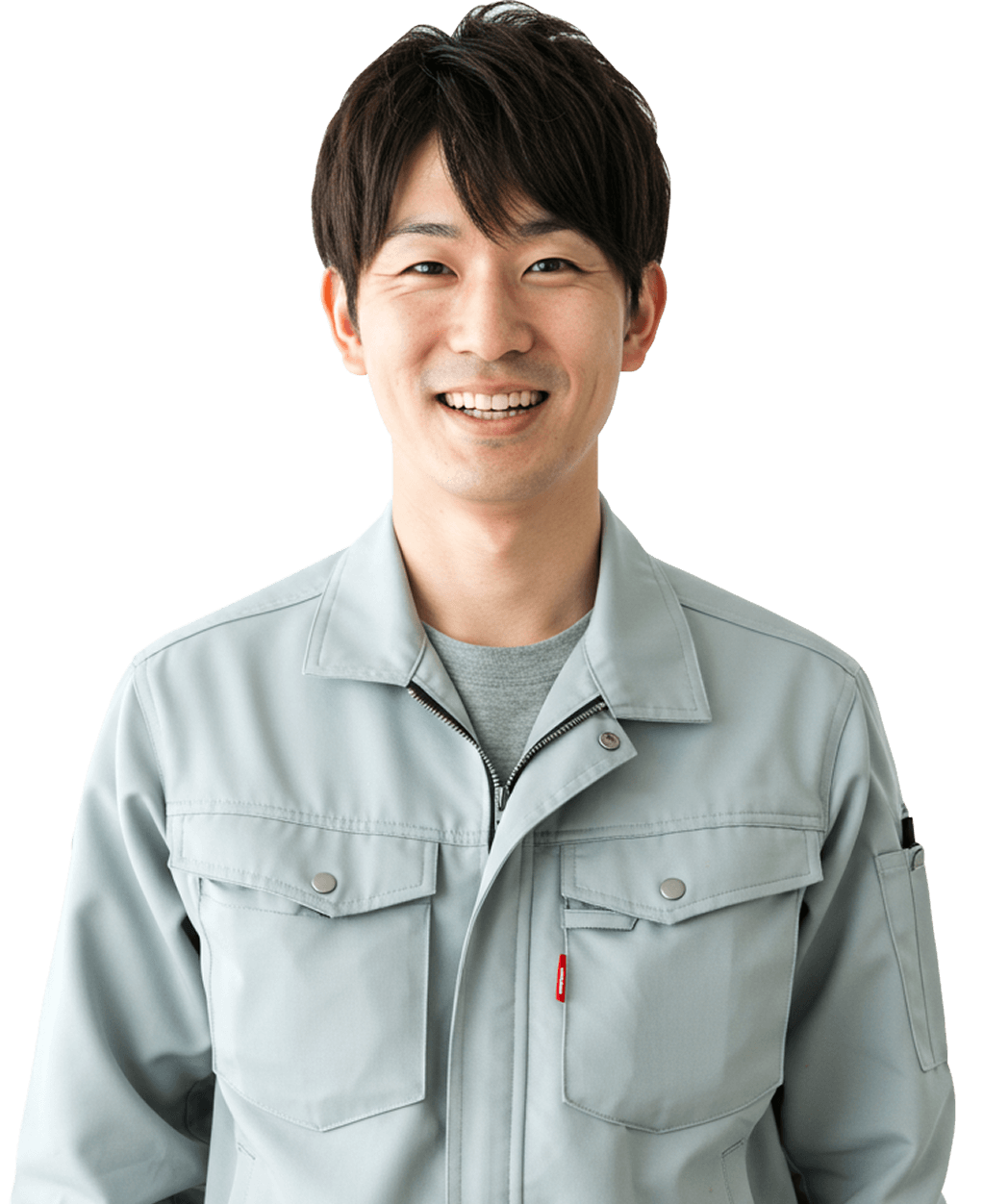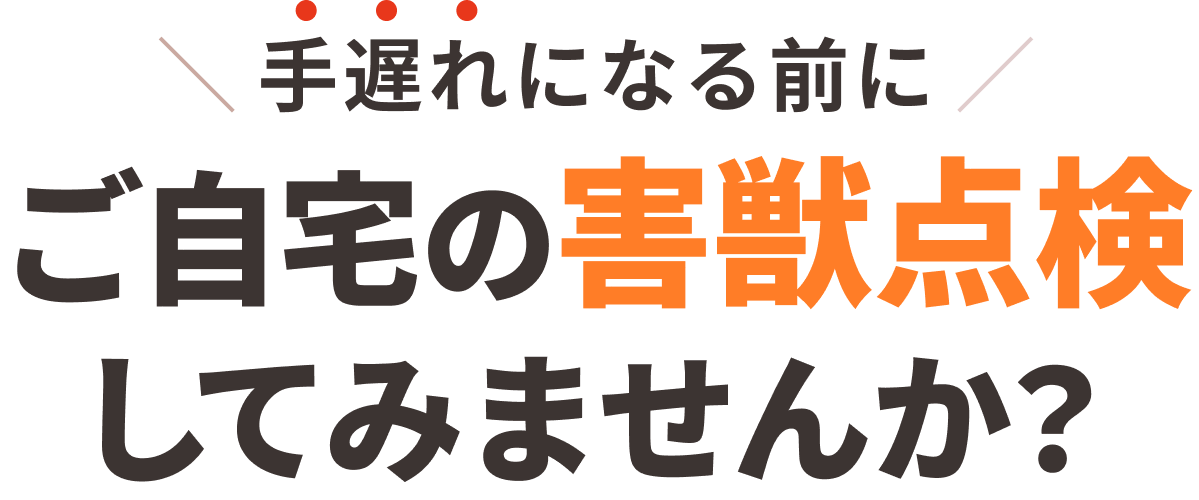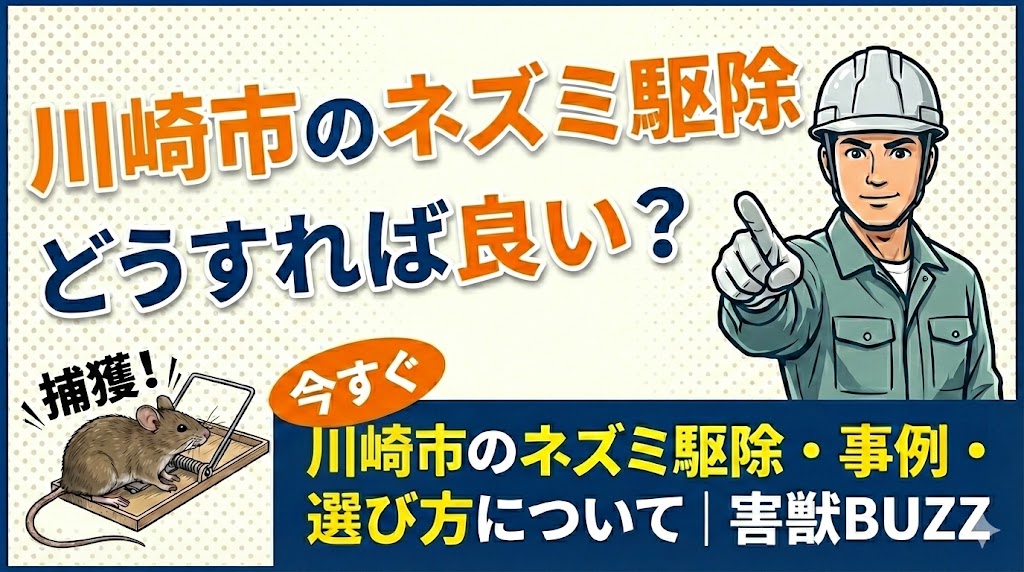アナグマを駆除する方法と知らないと損する注意点

自宅や敷地内にアナグマが侵入して困っている方は多いでしょう。アナグマは一度侵入すると、畑や庭を荒らしたり、床下に巣を作って建物を傷めたりといった被害を引き起こします。放置すると、衛生面や安全面でも問題が生じる可能性があるため、早めの駆除対策が必要です。
しかし、アナグマは法律で保護されており、許可なく捕獲・駆除することは禁止されています。適切な方法で駆除を行わなければ、法的トラブルになるおそれがあるのです。
本記事では、アナグマの適切な駆除方法や、知らないと損をする注意点についてわかりやすく解説します。アナグマによる被害を防ぎ、安心して暮らせるようになるために、ぜひ参考にしてください。
目次
アナグマを駆除する方法を3つ解説

アナグマが自宅や庭に侵入してしまったら、できるだけ早く駆除したいものです。本章では、自力でも実践しやすいアナグマの駆除方法を3つ、わかりやすく解説します。
- 柵・ネットで侵入を防ぐ
- 忌避剤を使う
- 光・音を使う
それぞれの方法を順番に解説しますので、ご家庭でのアナグマ駆除にお役立てください。
柵・ネットで侵入を防ぐ
アナグマを家の近所で見かけたら、柵・ネットの設置がオススメです。
アナグマは土を掘る力が非常に強く、小さな隙間でも容易に侵入します。そのため、アナグマが地中から潜り込めないように、柵やネットは少なくとも30cm~50cm程度、地面の下まで埋め込むことが重要です。
また、プラスチック製のネットでは簡単に破られてしまう可能性があります。できるだけ金属製の柵や金網を選び、侵入を確実に防ぎましょう。
アナグマは意外に小さな隙間でも通り抜けられます。ネットの網目は細かいものを選ぶと安心です。
忌避剤を使う
アナグマが家の中や庭など身近にいる場合、ニオイを活用した忌避剤による駆除が有効です。なぜなら、アナグマは臭覚が非常に敏感で、強い刺激臭を嫌う性質があるためです。
アナグマに対して効果が期待できる忌避剤としては、以下のようなものがあります。
| 種類 | 主な特徴・効果 | 使用時のポイント |
| 木酢液(もくさくえき) | 独特のくん製臭がアナグマを遠ざける | 原液を薄め、侵入口周辺に散布する |
| 唐辛子(カプサイシン) | 刺激臭、辛味成分で強力な忌避効果 | 粉末をまいて定期的に補充する |
| 市販の動物忌避剤 | アナグマ用のタイプを選べばより効果的 | 効果の持続時間を確認して補充する |
これらの忌避剤はホームセンターやショッピングサイトなどで手軽に手に入れられ、安価で使用しやすいです。侵入経路や巣穴の近くにまいておくだけで、アナグマを寄せ付けにくくなります。
忌避剤を使う際のポイントとしては、継続して使用することです。忌避剤のニオイは、特に雨が降った後などに流されやすいため、定期的に散布を繰り返しましょう。
光・音を使う
光や音を使った方法も、アナグマの駆除・追い出しに効果があります。なぜなら、アナグマは警戒心が強く、急激な光の変化や大きな音を嫌うためです。
光や音を利用した具体的な駆除方法として、以下の方法があります。
| 方法 | 期待できる効果 | 使用時のポイント |
| センサー式ライト | 突発的な光の照射により、侵入時にアナグマを驚かせ追い払う | アナグマの通り道や侵入口に設置し、定期的に動作確認をする |
| ラジオ・スピーカー | 人間の声や音楽を流し、気配を感じさせることで忌避させる | 夜間や不在時にも音を出すことで効果が高まる |
光や音は一時的には効果がありますが、継続して使用すると慣れてしまい、効果が弱まることがあります。そのため、定期的に設置場所や光・音の出力設定を変え、アナグマが慣れないよう工夫をしましょう。
また、近隣の住宅への迷惑にならないよう、適切な場所や音量を考慮して設置することも重要です。
アナグマを駆除する際の注意点

アナグマを駆除する際は、法律や安全性、近隣への配慮など多くの点に注意が必要です。誤った方法で対処すると、トラブルの原因になったり、思わぬ被害を招いたりすることもあります。
アナグマを駆除する際、特に注意しておきたい点は、以下の3つです。
- 再発防止策を行う
- 法律を遵守する
- 直接触れない
それぞれの注意点を順番に詳しく解説しますので、把握した上で効果的で安全なアナグマ対策を講じましょう。
再発防止策を行う
アナグマの駆除に成功しても、再び侵入される可能性は十分あります。そのため、駆除後の再発防止策が非常に重要です。
アナグマは縄張り意識が強く、過去に住み着いた場所に戻ってくる習性があります。また、別のアナグマにも「安全な場所」と認識されやすいため、再び被害にあうリスクが高いです。
以下に、アナグマによる被害の再発防止のために行いたい対策をまとめました。
| 再発防止策 | 詳細 |
| 侵入口の封鎖 | 床下、基礎部分、換気口などを金網やブロックで塞ぐ |
| エサとなるものを放置しない | 生ゴミ、ペットフードなどを屋外に出さない |
| 棲み家になりやすい場所の撤去 | 庭木の根元、ウッドデッキ下、廃材などの整理 |
| 忌避剤や音、光などの継続使用 | アナグマが近寄りにくい環境を維持する |
駆除と再発防止策をセットで考えることが、アナグマ対策の成功につながります。被害に悩まされ続けないためにも、駆除後の対応を徹底しましょう。
法律を遵守する
アナグマをむやみに駆除すると、法律違反になる可能性があります。アナグマの駆除を行う際は、「鳥獣保護管理法」の規定に従って適切な手続きを踏む必要があります。
鳥獣保護管理法
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生動物の乱獲を防ぐために定められた法律です。アナグマも保護対象に含まれています。
具体的には、無許可でアナグマを駆除・捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。
参考:e-GOV法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
自治体への申請
自力でのアナグマ駆除を検討する場合は、事前に自治体に申請し、所定の許可を得る必要があります。
以下に、自治体への申請手続きの大まかな流れをまとめました。
| 手順 | 詳細 |
| ①相談 | 市区町村の環境課・鳥獣担当窓口に被害状況を伝える |
| ②申請書の提出 | 「有害鳥獣捕獲許可申請書」などを記入・提出する |
| ③許可の取得 | 自治体が調査し、駆除が適切と判断された場合に発行される |
| ④捕獲・駆除の実施 | 許可条件を守って作業を行う |
| ⑤報告書の提出 | 終了後、捕獲・駆除数や方法を報告書にまとめて提出する |
アナグマは単なる害獣ではなく、鳥獣保護管理法で守られている野生動物です。焦ってすぐに駆除するのではなく、正しい手順を踏んで対応することが、住環境を守るうえでも重要です。
また、自治体によっては専門業者の紹介や補助金制度を設けていることもあるため、まずは相談から始めてみましょう。
直接触れない
アナグマを自力で追い出そうとしても、絶対に素手で触れたり、近づきすぎたりしないことが鉄則です。攻撃されたり、病原菌を移されたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
アナグマは臆病な反面、身の危険を感じると鋭い歯で反撃する可能性があります。また、SARS(重症急性呼吸器症候群)のような感染症リスクも報告されています。
なので、「アナグマを見つけたら触らず、すぐ相談」が最も安全で確実な対応です。万一、アナグマにかまれたり引っかかれたりした場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
アナグマの自力駆除よりも、安全を優先することを心がけてください。
アナグマの生態・特徴

アナグマは愛らしい見た目とは裏腹に、住まいに深刻な被害をもたらすことがある野生動物です。アナグマの行動範囲や習性を理解しておくことで、「どうして家に来たのか」「どうすれば来なくなるか」がわかり、根本的な対策がしやすくなります。
アナグマは夜間に活動する習性を持ち、地中に巣穴を掘る力に優れているため、人家の床下や畑などに被害を与えやすい動物です。見た目が似ていることから、タヌキに間違えられることもあります。
以下に、アナグマの主な特徴と生態をまとめました。
| 項目 | 詳細 |
| 分類 | 哺乳類(イタチ科) |
| 大きさ | 体長40〜60cm(尻尾は10~15cm程度)/体重12〜13kg程度 |
| 見た目 | 短足でずんぐりとした体形、顔に黒い縞模様(パンダのような模様) |
| 活動時間 | 夜行性(夕方から明け方まで活発) |
| 食性 | 雑食性(ミミズ、昆虫、果物、小動物など) |
| 巣の特徴 | 地中に深く複雑なトンネルを掘り、複数の出入口のある巣を作る |
| 行動パターン | 決まったルートを通って行動する「けもの道」を作る |
| 寿命 | 野生で10〜15年ほど |
参考:日本有害鳥獣駆除・防除管理協会「アナグマってどんな動物?見つけたらどうすべき?アナグマの生態や害獣被害を解説」
アナグマを放置することで発生する被害

アナグマの侵入を放置すると、思わぬ被害に発展するおそれがあります。「そのうち出ていくだろう」と安易に考えるのは危険です。実際にさまざまな問題が報告されている上に、駆除のタイミングを逃すほど対処が難しくなり、費用や手間も増大します。
アナグマを放置することで発生する主な被害は、以下の3つです。
- 農作物被害
- 穴掘り被害
- 床下での騒音や悪臭被害
それぞれの被害について順番に詳しく解説します。
農作物被害
アナグマを駆除せずに放っておくと、畑や庭の農作物が狙われ続け、作物の収穫量や品質の低下、経済的損失につながります。特に、果物や野菜などを栽培している家庭菜園や農地では、アナグマによる被害が発生しやすいです。
アナグマは雑食で、スイカ・トウモロコシ・イチゴ・ジャガイモなどの農作物も好んで食べるため、収穫前のタイミングで畑に入り込み、食い荒らしてしまいます。地中にいる虫を探すために、畑を掘り返す行動も見られ、作物の根を傷つけてしまうケースも少なくありません。
アナグマによる農作物被害は、一度始まると繰り返し発生する傾向があります。収穫の時期を狙って出没することも多く、農家にとっては収入減少や労力の無駄にもつながります。
穴掘り被害
アナグマは非常に力が強く、前足で地面を掘る習性があるため、畑だけでなく庭先や建物の下などあらゆる場所に穴をあけてしまいます。早期に対策を講じないと、被害が広がりかねません。
アナグマは、地下に長いトンネル状の巣を作るのが特徴です。また、地中のミミズや昆虫を探すために柔らかい土や芝生、畑などを好んで掘る傾向があります。そのため、人家の床下や畑、ビニールハウスの中などにも穴を掘りやすいです。
アナグマによる穴掘り被害は、時間とともに被害が拡大する傾向があります。最初は小さな穴でも、放置すれば地下に広がり、生活インフラや農業資材にまで被害が及ぶ可能性があります。
床下での騒音や悪臭被害
家の基礎部分や床下は暗くて湿度があり、外敵から身を守れる空間のため、アナグマにとっては格好の巣です。一度住み着かれると、夜間の活動音や糞尿による強い臭いが発生し、居住環境に深刻な悪影響を及ぼします。
アナグマは夜になると活動し始め、床下で動き回る音や鳴き声を立てることが多いです。また、糞尿を特定の場所に溜める「溜めフン場」を作る習性があるため、長期間放置すると悪臭が強まり、建物の腐敗や害虫発生の原因にもなります。
アナグマによる騒音・悪臭被害は、家族の健康や住宅の資産価値を脅かすリスクがあります。
以上、アナグマを放置することで発生する代表的な被害を解説しました。アナグマによる被害や身近にいるサイン(音やニオイ)を感じた時点で、侵入経路の封鎖や床下の点検を実施しましょう。また、必要に応じて専門の駆除業者に相談することをオススメします。
アナグマ駆除はお任せください!
アナグマを身近で見かけても、むやみに駆除しようとするのは危険です。アナグマは法律によって保護されているため、適切な対処が必要です。駆除や追い出しは、専門知識を持つ害獣駆除業者に依頼しましょう。
専門業者に依頼することで、安全かつ適切にアナグマを家から追い出すことが可能です。専門業者に依頼すると、以下のようにさまざまなメリットがあります。
- 適切な方法で、合法的に対応できる
- 侵入経路の特定・封鎖により、繰り返しアナグマが住み着くのを防げる
- 人体に害のない方法で追い出せる
- 糞尿の除去や消毒作業の徹底で衛生面でも安心できる
アナグマの駆除業者選びに悩んだら、害獣BUZZにお任せください。
私たちは、アナグマをはじめとする害獣の駆除だけでなく、侵入経路の封鎖・清掃・消毒など、再発防止まで考えた徹底的な対策をご提案する専門業者です。お客様のご予算やご要望に合わせた最適なプランを提供し、安心できる環境を取り戻すお手伝いをいたします。
実際に、「安心して任せられた!」という喜びの声を多数いただいております。アナグマのような動物による被害でお困りの方は、ぜひ 害獣BUZZ にご相談ください。当社は365日24時間対応し、迅速かつ丁寧な対応で、快適な暮らしをサポートします。
まとめ
アナグマの被害は放置せず、適切に駆除・再発防止対策を行うことが重要です。アナグマは一見おとなしく見える動物ですが、放置した場合の被害は想像以上に深刻です。農作物被害・床下騒音・悪臭・建物の破損といった被害が同時多発的に発生することもあります。
早めの対策で、アナグマによる被害を抑えやすくなります。自力での対処に限界を感じたら、無理をせず専門家へ相談し、法律を守りながら安心できる生活環境を取り戻しましょう。
害獣BUZZでは無料の現地調査を実施しておりますので、アナグマのような動物による被害でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |