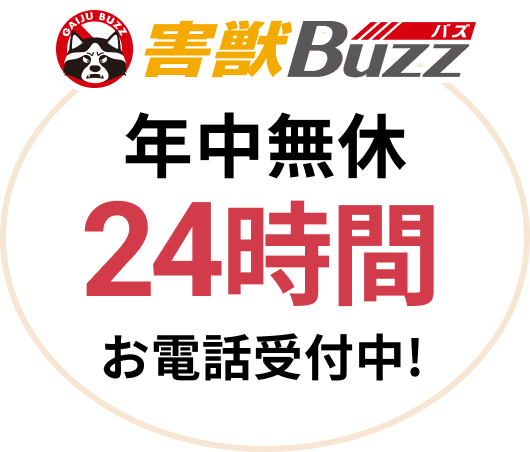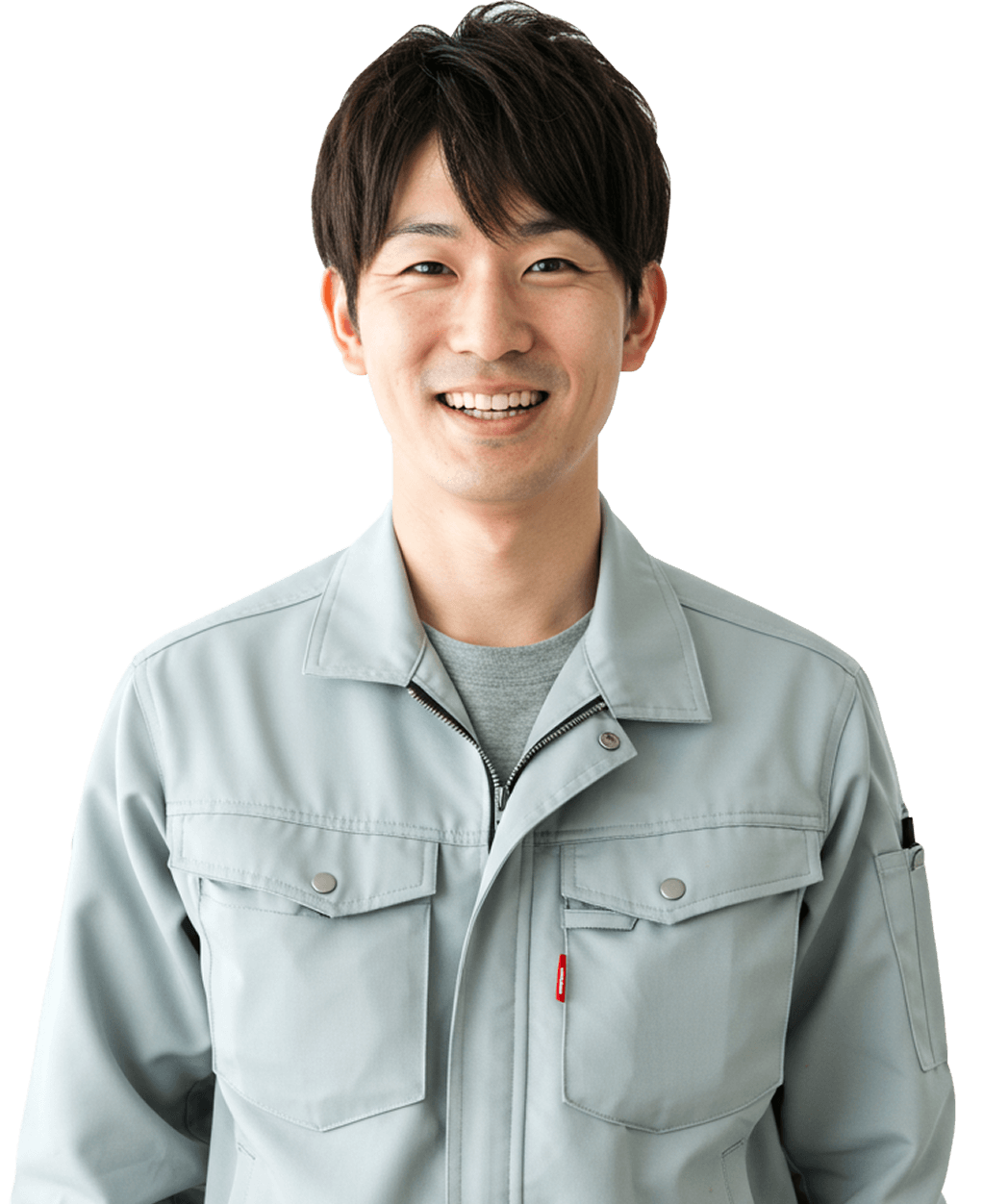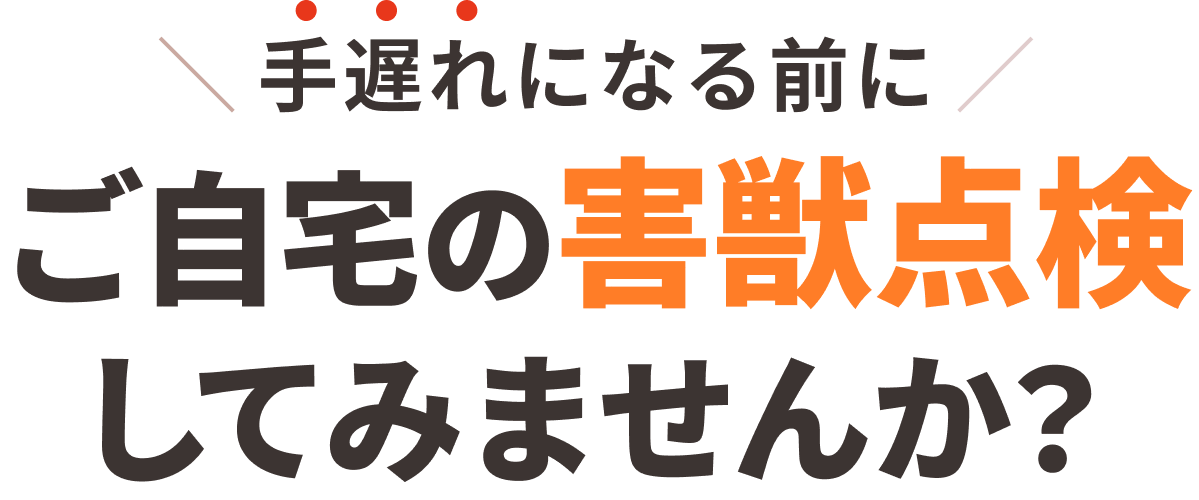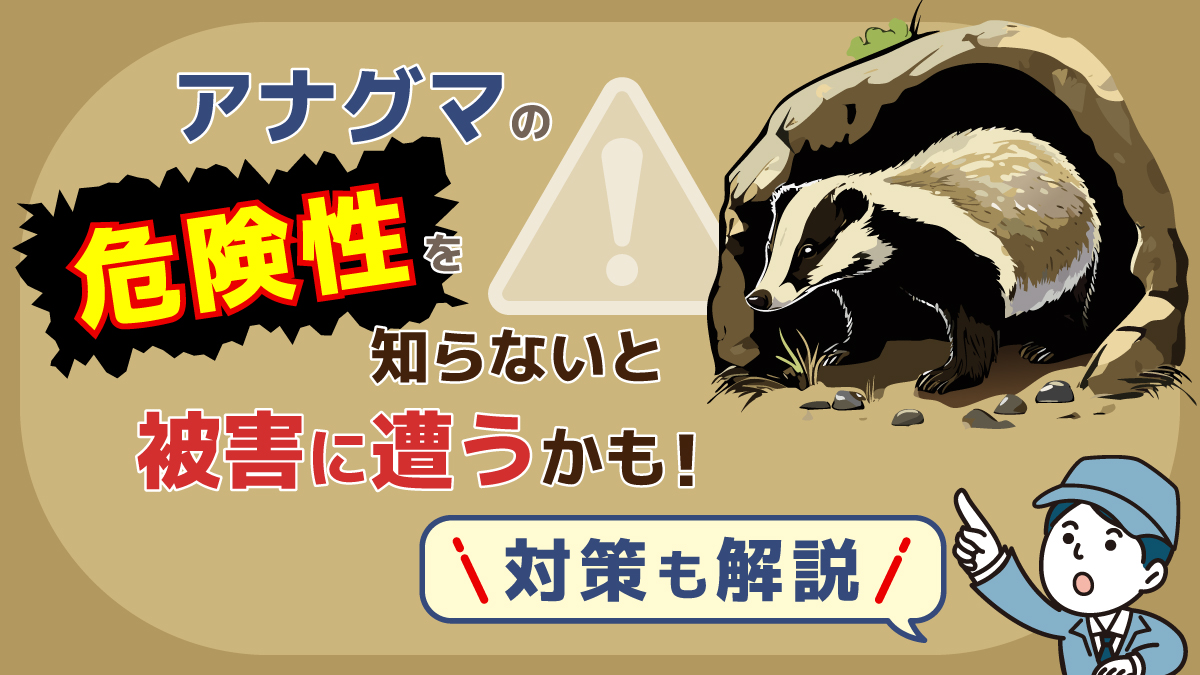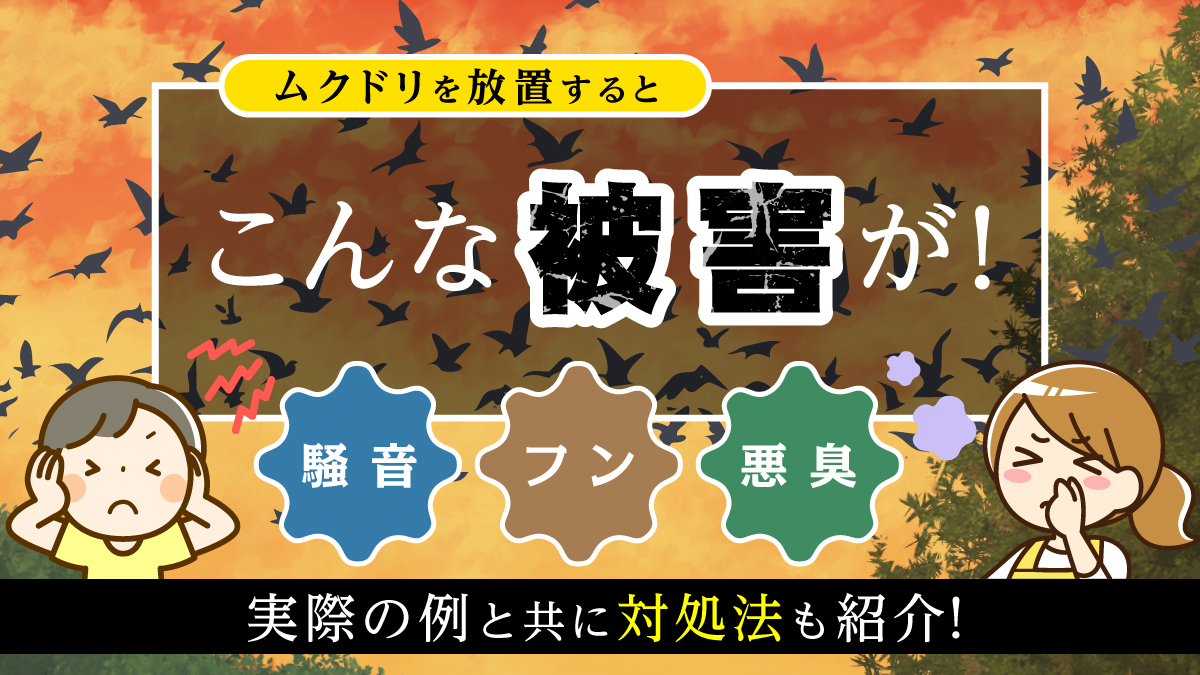アナグマのフンの特徴は?他の動物との見分け方も!

「庭や畑など身近な場所で見慣れないフンを見つけたけれど、何の動物のものかわからない…」と悩む人は多いのではないでしょうか。実はそのフンがアナグマのものである場合、早めの対策が求められます。
アナグマは一見かわいらしい姿をしていますが、農作物を荒らしたり、庭や建物の下に巣穴を掘ったりと、さまざまな被害を引き起こす野生動物です。そのため、フンを見つけた場合には、その動物がアナグマかどうかを迅速に判断し、被害拡大を防ぐための適切な対応を取りましょう。
本記事では、アナグマのフンの具体的な特徴をわかりやすく解説します。アナグマによる被害を早期に防ぎ、安心して暮らせるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
【形状・混在物・ニオイ】アナグマのフンの特徴を解説!

まずは、形状・混在物・ニオイといった観点から、アナグマのフンの特徴を解説していきます。
形状と大きさ
アナグマのフンは細長く、ソーセージ状または棒状の形をしていることが多いです。以下に、主な特徴をまとめました。
- 形状:細長い棒状で、やや丸みを帯びている
- 長さ:5〜10cm程度
- 太さ:1〜2cm程度
- 色:黒褐色〜茶色(食べ物によって多少変化)
フンに混ざっているもの
アナグマのフンには、食べたものの痕跡がそのまま残っていることが多く、内容物の観察が判別の手がかりになります。
以下に、アナグマのフンに混ざりやすい代表的なものをまとめました。
- ミミズの断片:赤褐色の細長い線状のもの
- 昆虫の殻・羽・足:黒っぽい硬いかけらや、キラキラした羽など
- 木の実の殻・種子:ドングリやクルミの破片が混ざることもある
- 果物の繊維や皮の一部:熟した果実を食べた際に残る繊維状の物質
- 動物の毛:ネズミなどの小動物を食べた痕跡(頻度は低め)
フンを発見した際は、内容物を観察して、早めの対策に役立てましょう。直接触れず、手袋やスコップを使って観察するなど、衛生面にも十分注意してください。
ニオイ
アナグマのフンはイタチのように強烈な悪臭を放つものではなく、やや土臭さや発酵臭が混ざったような自然系のニオイがする傾向があります。ニオイだけで完全に判別するのは難しいものの、「異常に強くないが、土臭くて気になる」程度のニオイであれば、アナグマの可能性を疑ってみましょう。
ただし、アナグマが食べたものによっては異臭が強くなる場合もあるため、「臭くないから安全」だとは限りません。
また、たとえニオイが弱くても、放置していると周囲の土壌や空気に悪影響を与えることがあります。雨に濡れると悪臭が強くなることがあり、特に梅雨や夏場は腐敗が進みやすいため要注意です。
アナグマのフンによる被害

アナグマのフンは、衛生面・ニオイ・景観・病原体のリスクといったさまざまな被害を引き起こします。特に人家の近くで繰り返し排泄されると、生活環境の悪化や健康被害につながる可能性があるため、早期の対策が必要です。
本章では、アナグマのフンによる代表的な被害として、以下の3つを取り上げます。
- 悪臭
- 健康被害
- 家屋の劣化
それぞれの被害について順番に詳しく解説します。
悪臭
アナグマのフンは、排泄直後は比較的ニオイが弱めですが、時間の経過や雨・湿気などで腐敗が進むと強烈なニオイを発するようになります。
特にアナグマには同じ場所をトイレ場として繰り返し使う「溜めフン」の習性があり、フンが蓄積していくとニオイが悪化し、近隣の生活環境にも影響を及ぼします。
以下に、アナグマのフンが原因となる悪臭被害の例をまとめました。
- 庭・玄関先にフンがたまり腐敗臭が漂い、不快感やストレスを感じる
- ベランダ・物置周辺のフンの臭気が室内に入ってしまい、窓を開けられなくなる
特に夏場や梅雨時期など湿気が多い季節には腐敗が進みやすく、ニオイがより強くなるため注意が必要です。また、一度フンをされた場所は、繰り返し狙われる可能性が高いため、すばやい処理とその後の対策を徹底し、清潔で快適な住環境を守りましょう。
健康被害
フンには多くの細菌や寄生虫が潜んでいる可能性があります。特にアナグマのフンに含まれる可能性のある病原菌や寄生虫には、「レプトスピラ症」「サルモネラ症」などが挙げられ、これらが人間やペットの健康を害するおそれがあります。
これらの感染症は、特に抵抗力が弱い子どもや高齢者、ペットがかかりやすいため、細心の注意が必要です。
感染症や寄生虫によるリスクを抑えるため、フンを見つけた際には迅速に処理し、その後の衛生管理や侵入防止対策を徹底することが重要です。
家屋の劣化
前述のとおり、アナグマは同じ場所で繰り返しフンをする「溜めフン」の習性があります。そのため、フンが蓄積すると、フンに含まれる水分や腐敗物質が住宅や物置の基礎、床下、外壁を徐々に傷めます。
特に床下や物置の下など湿気が溜まりやすい場所に排泄されると、フンの水分が木材や金属部分を腐食させる原因となり、建物の強度が低下します。
以下に、アナグマのフンによる家屋劣化の具体例をまとめました。
- フンによる湿気で木材が腐食し、床や土台の耐久性が低下する
- フンによる腐敗成分で外壁や塗装が傷み、補修が必要になる
- 金属部分が腐食し、錆や腐敗によって修理や交換が必要になる
早めにフンを処理し、家屋への侵入経路を塞ぐなどの対策を徹底することで、住宅の劣化を未然に防ぎ、安心できる住環境を保つことが重要です。
アナグマのフンを処理する方法

アナグマのフンを見つけたら、衛生面と安全面に十分配慮して速やかに処理することが大切です。フンには病原菌や寄生虫が含まれている可能性があるため、正しい手順で処理し、再発を防ぐ対策まで行うことが重要です。
本章では、アナグマのフンを適切に処理する方法を3つのステップに分けて取り上げます。
- 装備を整える
- フンを回収する
- 除菌・消臭を行う
それぞれの方法を順番に詳しく解説します。
装備を整える
アナグマのフンには、見た目ではわからない病原菌や寄生虫が含まれていることがあります。そのため、素手や無防備な状態で触れると感染症や健康被害を引き起こすリスクがあります。感染や二次被害を防ぐために、処理前にしっかりとした装備を整えることが欠かせません。
以下は、アナグマのフンを処理する際に準備するのが望ましい装備の一覧です。
- 使い捨て手袋:直接フンに触れることを防ぎ、感染リスクを減らす
- マスク:フンの粉じんやニオイ、病原体の吸入を防ぐ
- 長袖の衣服:肌の露出を避け、汚れや病原菌から体を保護する
- 使い捨てエプロン:フン処理時の衣服の汚れや付着を防ぐ
- ゴミ袋(厚手):フンを密閉して処理するために使用
- スコップやトング:直接手で触れないようにフンを回収するために使用する
適切な装備を準備し、安全に処理を行って、被害を最小限に抑えましょう。
フンを回収する
アナグマのフンを放置すると、悪臭や害虫発生の原因になるだけでなく、フンを通じて人やペットが感染症にかかるおそれがあります。特にアナグマには溜めフンの習性があるため、放置すれば被害が拡大する可能性が高まります。
以下に、アナグマのフンを安全に回収するための方法を紹介します。
- 防護具を装着する
- スコップやトングを使ってフンを回収する
- 回収したフンを厚手のビニール袋に入れる
- 袋をしっかりと結び、二重にして密閉する
- 可燃ゴミとして自治体のルールに従って廃棄する
安全で清潔な生活環境を守るために、フンの処理を怠らず、しっかりと対策を進めましょう。
除菌・消臭を行う
アナグマのフンにはレプトスピラ菌、サルモネラ菌などが含まれている可能性があります。また、フンのニオイがアナグマ自身を引き寄せることにもなりかねません。そのため、見た目の処理だけでなく、見えないリスクまで除去することが重要です。
以下に、アナグマのフンの処理後に行うべき除菌・消臭のステップをまとめました。
- 除菌剤を散布する:塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)やアルコール消毒液
- 消臭剤や石灰をまく:動物用消臭スプレー、木酢液、消石灰など
- 乾燥させる
塩素系の消毒剤は混ぜると危険なものがあるため、使用時は単独で使い、換気も行いましょう。
フンは一度処理しても再発しやすい

アナグマには溜めフンの習性があり、特定の場所を「トイレ」と認識して繰り返し利用する傾向があります。このため、一度フンを処理しても、同じ場所に戻ってきて再び排泄するケースが多いです。さらに、フンのニオイ成分が残っていると、アナグマにとってその場所がまだ使えるサインとなってしまいます。
ニオイの除去や物理的バリアの設置、環境の改善を組み合わせた多角的な再発防止策を講じることで、ようやくフン被害を根本から断ち切れます。手間を惜しまず、長期的な視点での対策を心がけましょう。
フンの清掃はお任せください!
アナグマによる被害をしっかりと解決するためには、アナグマの潜伏場所を突き止めて追い出す必要があります。その後、糞尿の清掃と除菌を行い、最後に侵入経路を確実に塞ぐという、非常に多くの工程が必要です。
こうした作業は専門的な知識と経験を要するため、慣れていない方が行うと失敗のリスクも高くなります。不安がある場合は、専門の駆除業者に依頼するのが確実です。
アナグマ対策で信頼できる業者をお探しであれば、ぜひ「害獣BUZZ」にお任せください。当社は、数多くのアナグマ駆除を手がけてきた実績を持ち、現地調査をもとに最適な対策プランをご提案・実行いたします。
自社施工にこだわっており、調査から駆除、侵入経路の封鎖、フンの清掃・除菌までを一貫して対応可能です。下請けを使わないことで、サービスの質を保ちながらコストも抑えています。
また、再発防止にも力を入れており、多くの場合で保証もご提供可能です(保証内容は現地調査のうえご案内いたします)。
「フンを見かけた」「異音がする」など、少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。早めの対応が、被害拡大を防ぐ第一歩です。
まとめ
フンには病原菌や寄生虫が潜んでおり、悪臭や建物の腐食など、見た目以上に多くのリスクを抱えています。さらに、アナグマの溜めフンの習性によって、一度排泄された場所が繰り返し狙われる可能性が高いため、処理後の対応が極めて重要です。
アナグマのフンを発見したときは、「たかがフン」と油断せず、きちんと観察・判断・対策を行うことが大切です。被害の拡大を防ぐには、正しい知識と準備が欠かせません。
慣れていないと失敗する可能性が高いうえに、身近でフンをしている害獣を特定する作業も求められるため、対策に不安があればプロの駆除業者に依頼することが望ましいです。
害獣BUZZでは無料の現地調査を実施しております。「身近でアナグマのものらしいフンを見かける」「フンによる悪臭や健康被害が怖いので、一刻も早く対策してほしい」と思われている方は、お気軽にお問い合わせください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |