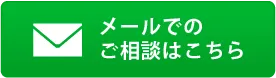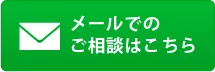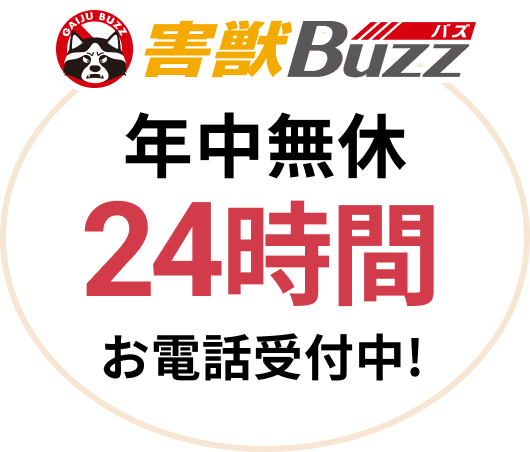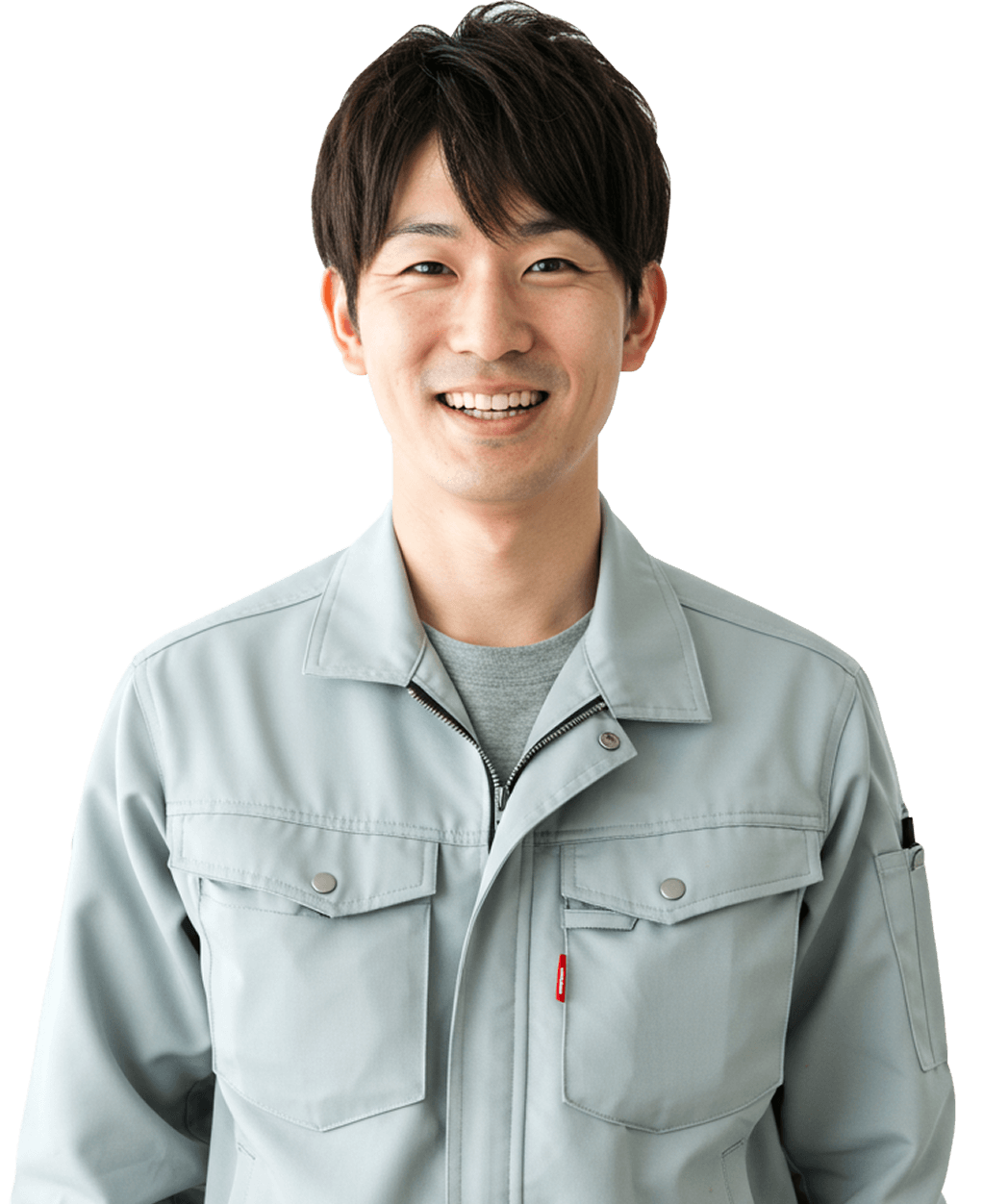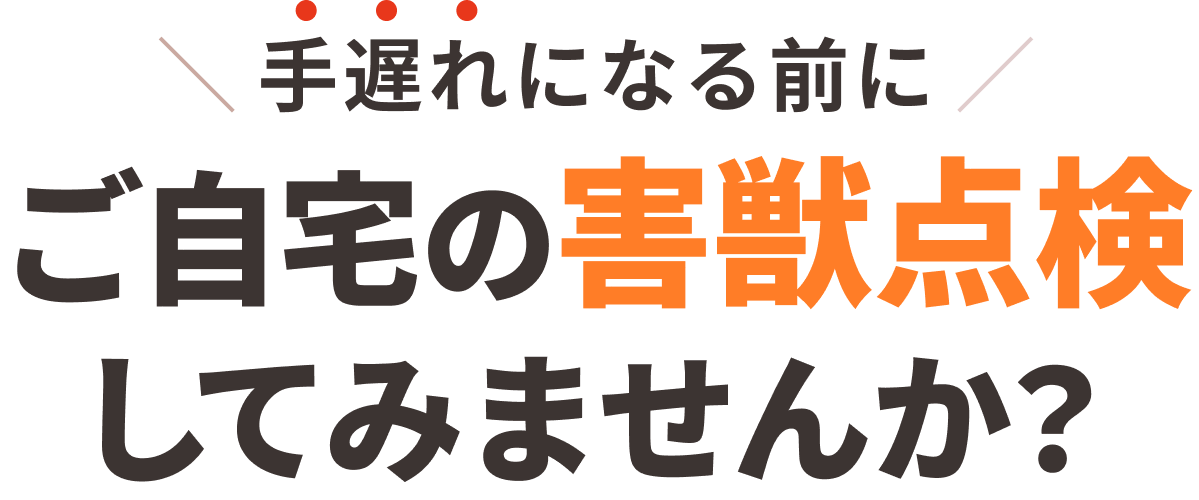イタチ被害は主に5パターン!個人でできる対策方法も解説

「夜になると天井裏から音がする」「家の中で異臭がする」と感じたら、イタチが住みついているかもしれません。
小柄で可愛らしいイタチですが、実は一晩でニワトリ小屋を全滅させるほど凶暴な肉食獣です。
狭い隙間から侵入し、家屋を荒らすだけでなく、悪臭・感染症・ペット被害など多方面に被害を及ぼします。
本記事では、イタチが引き起こす主な5つの被害と、個人でできる応急処置、再発を防ぐために必要な正しい駆除方法を詳しく解説します。
イタチの習性を理解して的確に対処し、安心して眠れる暮らしを取り戻しましょう。
目次
イタチの被害は主に5つ!各被害の詳細を解説

イタチは夜行性で人目につきにくい一方、生活環境に深刻な影響を与える動物です。繁殖力が非常に高く、放置すると被害は短期間で拡大します。
足音や鳴き声による騒音、フンや尿による悪臭や家屋の腐食、ノミ・ダニなどの健康被害、さらにはペット・家畜への被害まで多様です。
ここでは主な5つの被害をみていきましょう。
騒音被害
イタチは夜行性で、活動のピークは人が眠る深夜から明け方にかけてです。
屋根裏や天井裏に侵入すると、ドタドタと走り回る足音や鳴き声が響き渡ります。体長30cm前後と小柄ながら、動きが俊敏で音の発生場所が特定しにくいのが特徴です。
繁殖期(春〜初夏)には鳴き声や争いも増え、騒音はさらに激しくなります。
物音は一晩中続くこともあり、睡眠不足やストレス、体調不良につながる恐れがあります。
悪臭被害
イタチは溜めフンと呼ばれる習性を持ち、同じ場所に繰り返し排泄するため、屋根裏や床下にフンや尿が溜まり、時間とともに強烈な臭いが家全体に広がります。
さらに、肛門付近の臭腺(しゅうせん)からも強い分泌臭を放ちます。屋根裏など密閉された空間で放たれたニオイは部屋の中まで染み込み、日常生活に支障をきたすほど強烈です。
布や木材に染みつくと消臭剤では除去できず、放置すればカビや腐食の原因にもなります。
家屋への被害
屋根裏や床下は暖かく安全なため、イタチの巣作りには格好の場所です。イタチは断熱材を引き裂いて寝床にするため、断熱効果が失われ、破損箇所から湿気が入り込んでカビや腐食が進行します。
さらに、フンや尿によって木材が常に湿った状態によりシミがつき、進行すると梁や天井板が腐る場合もあります。
また、巣作り後も屋外と屋内を行き来するため、ノミやダニが繁殖し衛生環境の悪化を招きます。
被害が進行すればリフォームや天井板の張り替えが必要になり、修繕費が高額になるケースも少なくありません。天井のシミや異音を感じた段階で、早めの点検と対策を行うことが被害拡大を防ぐ鍵です。
健康被害
イタチの体にはノミやダニが多く寄生しており、人やペットに深刻な健康被害を及ぼす恐れがあります。特に屋根裏に棲みつくと、ノミやダニが家中に拡散し、かゆみ・湿疹・アレルギーを引き起こすこともあります。
また、イタチから感染する恐れのある主な感染症には以下があります。
- レプトスピラ症:発熱・頭痛・筋肉痛などを伴い、重症化すると腎障害や黄疸を引き起こす感染症
- サルモネラ感染症:フンや尿を介して感染し、下痢や腹痛、発熱を起こす食中毒の一種
- 鼠咬症(そこうしょう):イタチに咬まれることで感染し、発熱や関節痛、皮膚の腫れを引き起こす細菌感染症
参考:動物由来感染症ハンドブック2018
レプトスピラ症
サルモネラ感染症
鼠咬症
イタチを追い詰めると噛みつかれる危険があるので、咬傷を受けた場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
屋根裏や庭でフン・尿を見つけた際は、素手で触れずに手袋・マスクを着用し、清掃後には必ず除菌を徹底してください。
イタチに噛まれた際の対処法については、以下の記事で解説しています。
ペット・家畜への被害
イタチは雑食ですが、肉食傾向が強く小動物を襲う習性があります。屋外で飼うニワトリやウサギなどが狙われる場合が多く、活動が盛んな夜間に侵入します。
わずか3cmの隙間からでも入り込むため、ケージや金網の小さなズレは致命的です。
イタチは一夜でニワトリ小屋を全滅させる例もあるとされるほど獰猛で、捕食だけでなく巣を作って居座るケースもあります。
屋外飼育では、金属製ネットで隙間をふさぎ、センサーライトや防犯カメラを併用するなど物理的な防御と環境整備が重要です。
参考:今度はイタチ(テン?)が夜襲、ニワトリ小屋へ侵入し1羽が負傷
個人でもできるイタチ被害の応急処置
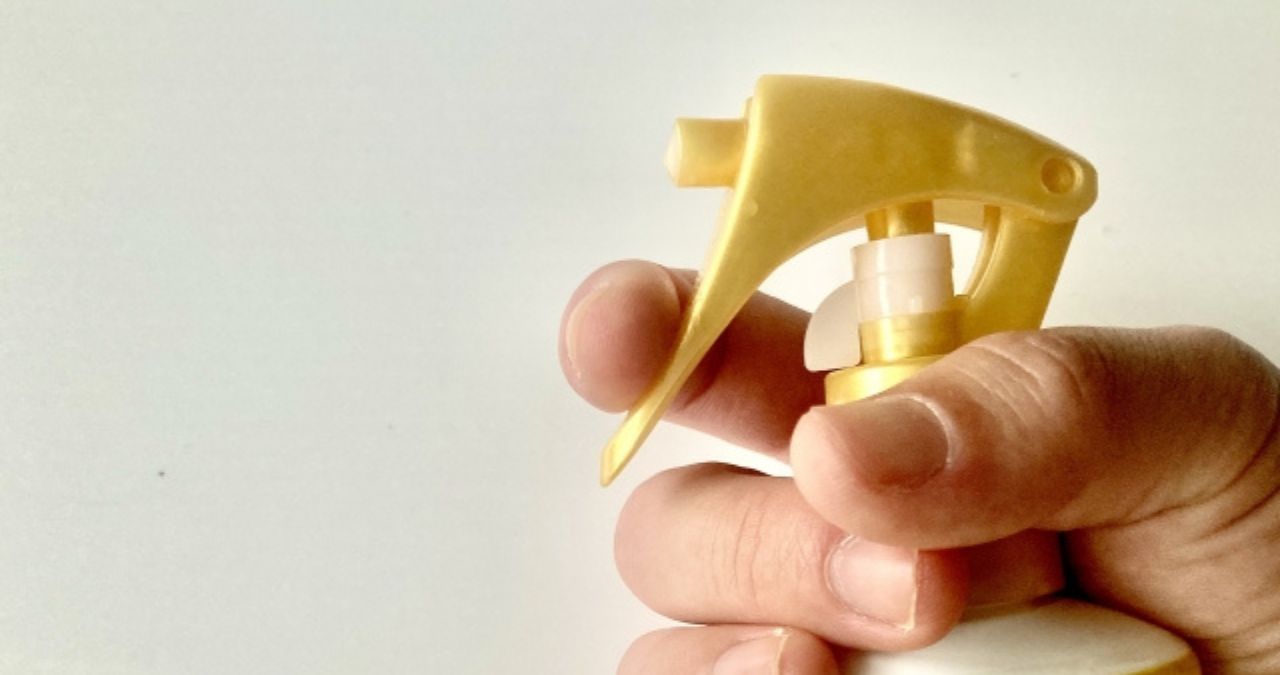
イタチによる被害を確認したら、できるだけ早く初期対応を行いましょう。
応急処置としてできることは主に、忌避剤を使った追い出しとフン・尿の清掃の2つです。専門的な知識がなくても実践でき、被害の拡大を一時的に食い止める効果があります。
ここでは、それぞれの手順と注意点をわかりやすく解説します。
忌避剤を用いた追い出し
イタチは嗅覚が非常に発達しており、強い刺激臭を嫌う動物です。
漂白剤・木酢液・お酢・くん煙などのニオイは、イタチが苦手とするもので家庭でもすぐに試せます。ただし、自然素材のニオイは効果が一時的で、こまめな再散布が必要になります。
より確実な対策としては、イタチ専用忌避剤の使用がおすすめです。ホームセンターや通販では、煙・スプレー・固形タイプなどさまざまな製品が販売されています。
屋根裏や床下の通り道、フンや足跡がみられる場所に設置し、出入り口の反対側から外へ誘導するように設置しましょう。
イタチ対策の忌避剤については、以下の記事で解説しています。
マーキングとなるフン・尿の清掃
イタチは溜めフンと呼ばれる習性があり、同じ場所で繰り返し排泄することで縄張りを示します。
フンや尿を放置すると自分の巣と認識され、再び戻ってくる原因になるため、追い出し後は必ず清掃と除菌を行いましょう。
清掃時はゴム手袋・マスク・ゴーグルを着用し、直接触れないように注意してください。
イタチの排泄物にはサルモネラ菌やレプトスピラ菌などの病原菌が含まれる可能性があり、対策が欠かせません。
清掃後は漂白剤やアルコールでしっかりと除菌したうえで、消臭剤や忌避剤を併用すると効果的です。
本格的な対策は個人で行うのが難しい理由

忌避剤や清掃で一時的に追い出すことはできますが、根本的な解決には専門知識が必要です。
イタチは学習能力が高く、わずかな隙間からでも再侵入するうえ、法律で保護されているため無許可での捕獲はできません。
ここでは、個人対応が難しい主な理由を2つの視点から解説します。
再発対策(封鎖施工)は難易度が高い
イタチはわずか3cmの隙間があれば容易に侵入でき、屋根裏・換気口・配管まわりなどの経路を使って出入りします。侵入口をみつけだして完全に塞ぐには、建物構造の理解と専門的な施工技術が必要です。
また、封鎖のタイミングを誤ると、内部にイタチを閉じ込めてしまうリスクもあります。死骸や悪臭など、かえって被害が悪化するケースも少なくありません。
確実に再発を防ぐには、追い出し・清掃・封鎖までを一貫して行える専門業者に依頼するのが安全で確実です。
鳥獣保護法を厳守しなければならない
イタチは鳥獣保護法で保護されており、オスの殺傷やメスの捕獲・殺傷が禁止されています。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあるため、個人での駆除は避けましょう。
また、毒餌を使った駆除も規制対象で、捕獲と同様の罰則が科されるため注意が必要です。
自治体によっては、申請・許可を得て捕獲を行える制度を設けている場合もあります。ただし、手続きには時間がかかるため、法律を順守して対応できる専門業者への依頼が確実です。
イタチ駆除の法律や手続きについては、以下の記事で解説しています。
イタチ駆除は害獣BUZZにお任せください

イタチ被害を根本的に解決するには、追い出すだけでなく侵入口の封鎖や再発防止策を徹底することが不可欠です。
しかし、警戒心が強く学習能力も高いため、個人での対応では再侵入を繰り返すケースも少なくありません。
さらに、イタチは鳥獣保護法の対象動物であり、許可なく捕獲・駆除を行うと法律違反となる恐れがあります。
害獣BUZZでは、現地調査や見積もりを無料で行い、建物の構造や被害状況を確認したうえで、最適なプランをご提案します。すべての作業を法律に則った安全な方法で実施するため、法的リスクを避けながら確実な駆除が可能です。
「夜中に天井裏で音がする」「部屋に異臭がする」などのサインを感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
イタチは警戒心が強く学習能力も高いため、放置すると被害が拡大しやすい厄介な動物です。
夜間の騒音や悪臭、フンや尿による感染症、家屋の腐食など、被害は精神面・健康面・経済面のすべてに及びます。
応急処置として忌避剤の使用や清掃で一時的に追い出すことはできますが、根本的な解決にはプロによる侵入口の封鎖と再発防止施工が欠かせません。
早めの相談が、安心で快適な暮らしを取り戻す第一歩です。イタチ被害にお困りの方は、ぜひ害獣BUZZまでご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |