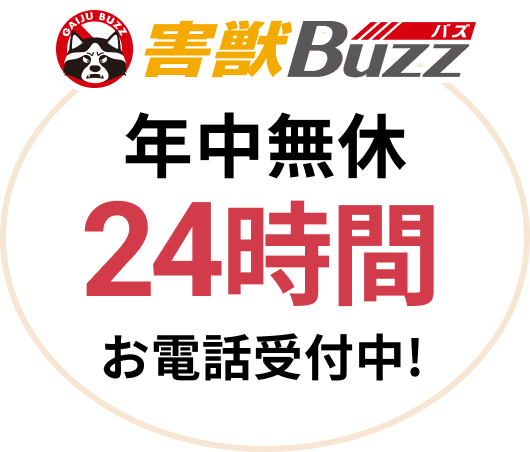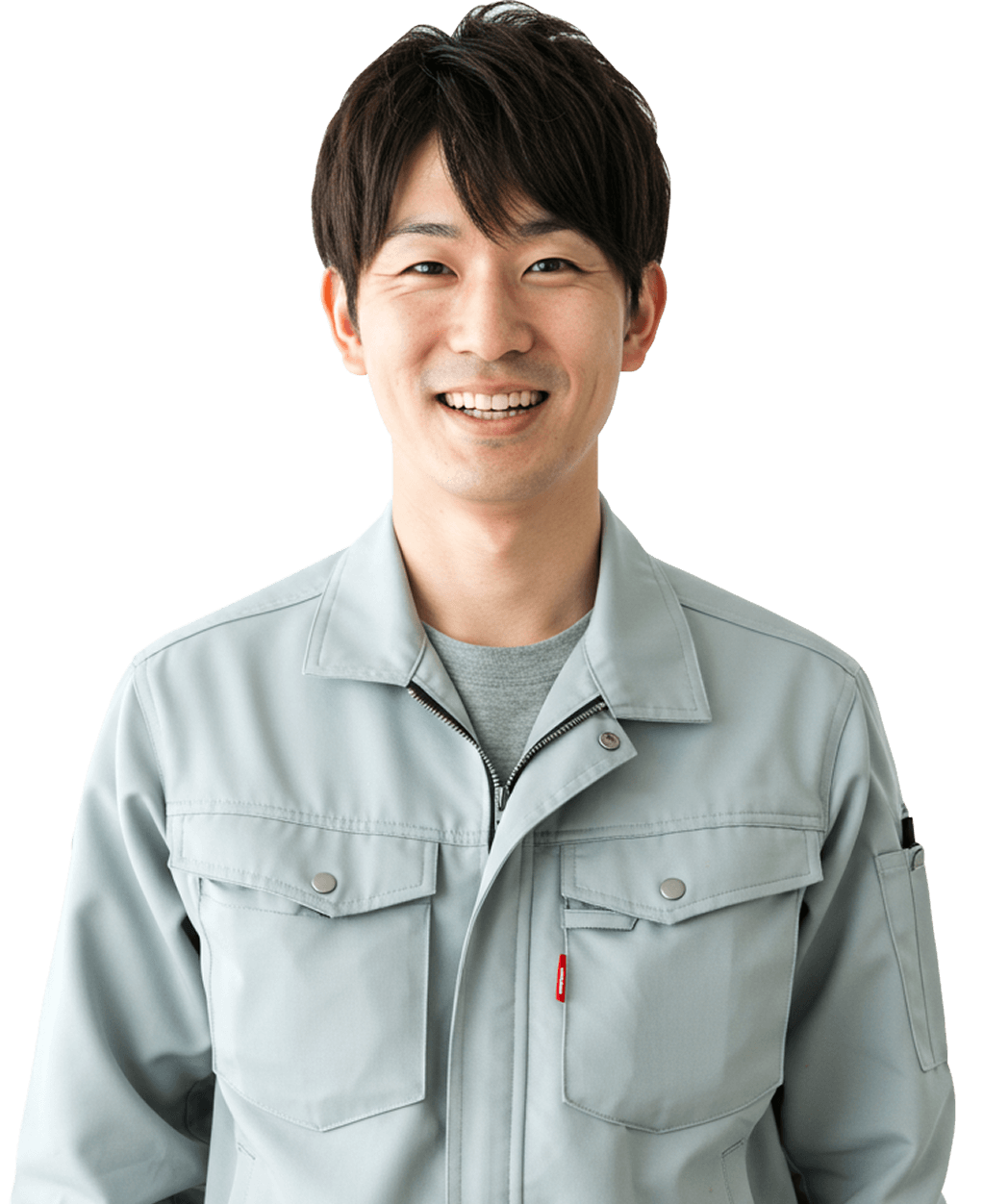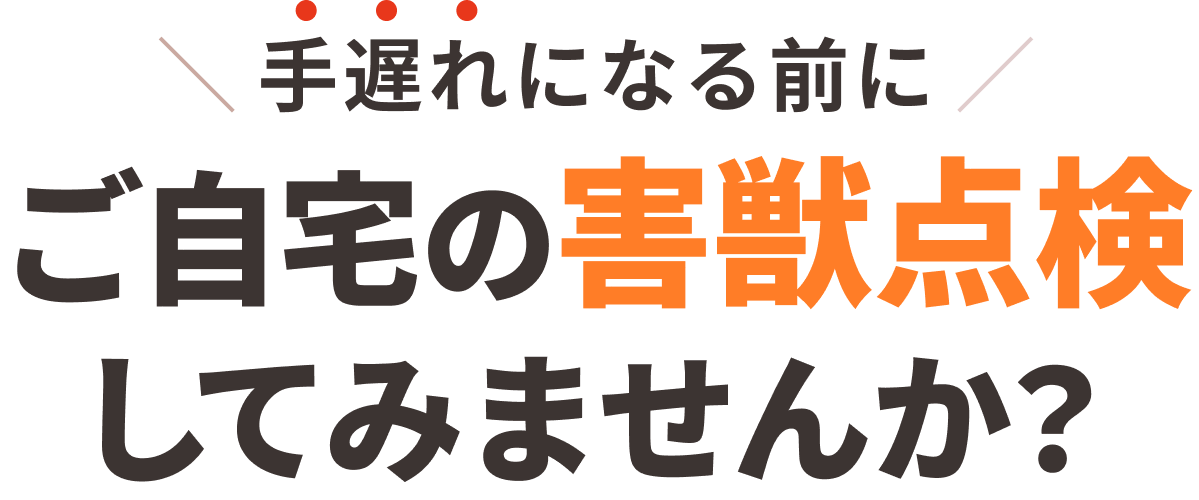コウモリが1匹いたら複数いる?見つけたら行うべき対策をプロが解説

コウモリは夜行性の動物で、人間の目に触れることは少ないですが、それでも家に侵入してくることがあります。
実はコウモリが家に1匹いたら、すでに数匹住み着いているか、今後住み着く可能性があるので要注意です!
コウモリは感染症の媒介や衛生面の悪化というトラブルを起こす一方で、法律で保護されており、対処の方法が難しいと考えられています。
この記事ではコウモリが家に1匹いたら複数いるおそれがある理由や、見つけたら行うべき対策を解説しますので、被害が拡大する前にできるだけ早期に対策してください!
- この記事をまとめると
- 1匹見つけたら複数いる可能性が高い。コウモリは集団で巣を作り、繁殖力も弱くないため、見えない場所に隠れている。
- 許可のない捕獲や殺傷は鳥獣保護法で禁止されている。また、糞尿には感染症の原因となる細菌やウイルスが含まれる。
- 安全な駆除には専門知識が必須。追い出し後の清掃・消毒、そして再発を防ぐための侵入経路の封鎖までが対策となる。
\相談だけでもOK! プロによる無料の現地調査&お見積もりはこちらから/
目次
コウモリが家に1匹いたら複数いるおそれがある

コウモリが家に1匹いたら複数いるおそれがあります。
なぜならコウモリは集団で営巣する習性があるからです。
私たち害獣BUZZが過去に駆除したケースでは、お問い合わせの段階では1匹だけだと伺っていても、実際に現地調査や駆除を行うと見えない場所に数十匹隠れていることも珍しくありませんでした。
また、予想以上のフンの数に驚かれる例も少なくありません。
「何匹いるのかもわからず不安」とお問い合わせいただいた事例をご紹介しますが、こちらも屋根裏に大量のフンがありました。
巣をつくる場所としては屋根裏や壁の隙間などが挙げられます。
コウモリは飛行するために多くのエネルギーを消費するので、熱ストレスを避けるために適切な温度、湿度の場所を探し、そこに定住しようとします。
参考:農業用水路トンネルとコウモリ類 – 農林水産省
洞穴性コウモリ類の保全対策と国営土地改良事業での活用について
そして一度巣を作ると、同じ場所に何年も続けて戻ってきます。
またコウモリは繁殖期になると、数百匹から数千匹の大群を形成することもあります。
参考:国立環境研究所 侵入生物DB
国土技術製作総合研究所 コウモリ類調査を実施するための基礎知識
そのため、家で1匹のコウモリを見かけたとしても、実際にはもっと多くのコウモリが隠れている可能性が高いです。
日本で家に住み着くのはアブラコウモリ
日本で家に住み着くのはアブラコウモリで、体の長さはだいたい5cm程度です。
アブラコウモリは小さなサイズではありますが、繁殖力は弱くないので注意しなければなりません。
アブラコウモリは毎年のように出産し、1回で2匹前後の子どもを産みます。
つまり、もともとの親コウモリを含めると、2年で6匹になるのです。
「それくらいならそこまで心配しなくても良いのでは?」と思ったかもしれません。
しかし、産まれた子どもも10ヶ月程度で繁殖できるようになるので、どんどん増えていきます。
見えているコウモリが全てではなく、屋根裏にすでに繁殖可能なコウモリが複数いるおそれもありますので、早めの駆除が必要です。
コウモリを見かけやすい場所は?

前述のようにコウモリを見かけやすい場所は、屋根裏や壁の隙間などです。
また当然ですが、野生動物なので森林や洞窟などの自然環境にも多く生息しています。
これらの場所によくコウモリが現れる理由は、コウモリにとって適した休息や繁殖の場所だからです。
さらにコウモリは小さくて柔軟な体をしているので、直径1〜2cm程度の穴でも通り抜けることができます。
そのため屋根や壁にある小さな穴や、亀裂などあらゆる隙間からの侵入も想定しておきましょう。
それに加えてコウモリには下記の特徴があります。
- 夜行性である
- 高周波音で方向感覚を得ている
高周波音は人間に聞こえることがあり、キーキーという高い音です。
これらの音や姿をコウモリの活動時間帯である夕方から夜に家の中で見聞きしたら、コウモリが侵入している可能性もあります。
もし侵入されてしまったなら戸締まりはもちろん、コウモリ用の対策をしましょう。
対策方法に悩むようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください!
\相談だけでもOK! プロによる無料の現地調査&お見積もりはこちらから/
コウモリを見つけたら行うべきこと

コウモリを見つけたら行うべきことは、追い出し、清掃、侵入経路の封鎖です。
これらの作業は、感染症の予防や法律での保護などを考慮しながら行わなければなりません。
追い出し
コウモリを追い出すには、まずコウモリが巣を作っている場所の特定が必要です。
前述した内容を踏まえてコウモリの巣の場所を特定しましょう。
場所が特定できたらいよいよ追い出しの実行に移るわけですが、自力での追い出しの場合には市販の忌避剤を利用する必要があります。
忌避剤の種類は主に下記の4つに分けられます。
| 忌避剤の種類 | 概要と使用法 |
|---|---|
| スプレータイプ | コウモリが嫌うニオイや成分を含む液体を、局所的に散布するタイプの忌避剤 コウモリが出入りする穴や巣に直接吹きかけて使用する |
| ジェルタイプ | コウモリが嫌うニオイや成分を含むゼリー状で置き型のタイプの忌避剤 コウモリが出入りする穴や巣に近い場所に置いて使用する |
| くん煙剤タイプ | コウモリが嫌うニオイや成分を含む煙を発生させ、屋内に充満させるタイプの忌避剤 コウモリが巣を作っている場所に置いて使用する |
| 固形タイプ | コウモリが嫌うニオイや成分を含む錠剤のような忌避剤 コウモリが巣を作っている場所に置いて使用する |
清掃
コウモリを追い出した後は、巣があった場所の清掃をしましょう。
理由としてコウモリは大量の糞や尿を排泄するので、悪臭やカビの原因になることがまず挙げられます。
またコウモリの糞や尿には、ライサイクロスピラ症や日本脳炎などの感染症の原因となる細菌やウイルスが含まれています。
参考:人と動物の共通感染症に関するガイドライン
動物由来感染症を知っていますか?
これらに触れたり吸い込んだりすると、人間にも感染する可能性があります。
そのため、清掃の際にはマスクや手袋などの防護具の着用が必須です。
また、清掃後は手洗いや消毒も忘れずに行いましょう。
侵入経路封鎖
侵入経路の封鎖は、コウモリが再び家に入ってこないようにするために必要です。
コウモリは一度巣を作った場所に執着します。
したがって追い出されても、一度侵入した場所には再侵入を繰り返すでしょう。
そのため、コウモリが入ってきた穴や亀裂をしっかりと塞がなければなりません。
ちなみにコウモリの侵入経路で代表的なものは下記の通りです。
- 窓の隙間
- ドアの隙間
- 通気口の隙間
- 配管の隙間
- 壁の穴
- 天井裏の隙間
前述のようにコウモリは、1〜2cmの隙間であれば容易に通り抜けることができるので、上記ような狭い隙間でもすり抜けられないような施工が必要です。
具体的には金網やパンチングメタルなど目が細かくて頑丈なもので、隙間を塞ぐようにしましょう。
また侵入経路の封鎖は、コウモリが巣を作っている場所だけでなく、これから侵入経路になりそうな場所に関しても予防を兼ねて全て行っておくことをオススメします。
コウモリ駆除はプロに依頼するのがオススメ

コウモリ駆除はプロに依頼するのがオススメです。
その理由は以下の3つが挙げられます。
侵入経路封鎖に危険を伴う
コウモリは飛行が可能な動物なので侵入経路封鎖時には高所作業が必要です。
またコウモリは屋根裏や壁の隙間などに侵入してねぐらにします。
これらの場所にアクセスするためには、はしごや足場などを使って高いところに登らなければなりません。
高所作業は転落や落下物などの事故のリスクが高く、安全対策が必要です。
また高所や狭いところからも侵入可能なことから、侵入経路の封鎖は一般の方では難しく、成功率は低いでしょう。
失敗したコウモリ対策では、被害再発を繰り返す可能性があります。
感染症の罹患リスクがある
前述しましたがコウモリは感染症を媒介します。
コウモリに噛まれたり引っかかれたりすると、感染症にかかる可能性がゼロではありません。
またコウモリの糞や尿に含まれる細菌やウイルスも同じように人間に感染する可能性があります。
参考:コウモリ由来のウイルスとその感染症
なぜ、コウモリはウイルスの宿主でいられるのか? 名大が理由の一端を解明
こういったリスクを避けるためにもコウモリ駆除は自分で行うのではなく、専門的な技術や知識、経験を有するプロに任せるべきです。
駆除に法的リスクがある
コウモリは鳥獣保護管理法という法律で保護されている動物です。
届け出なくコウモリを殺したり捕まえたりすることは禁止されています。
違法駆除を行ってしまうと1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金といった刑罰の対象になる可能性があります。
そのため、コウモリ駆除は法律を守って行わなければなりません。
プロに依頼すれば法律面に関してノーリスクで駆除を行えます。
コウモリの駆除については私たちにお任せください!
コウモリ被害に悩んでいる方は、自分で駆除しようとせずに、害獣BUZZにお任せください。
害獣BUZZは、コウモリを含む害獣被害の専門家です。
まずは無料の現地調査でお客様の被害状況を把握し、最適な駆除方法をご提案・施工します。
感染症の予防や法律の遵守はもちろん、再発防止まで欠かしません。
さらに駆除後のアフターケアにも力を入れており、業界トップクラスの最長10年保証のプランもご用意可能です。
駆除して終わりではなく駆除後も長くパートナーとしてお客様に寄り添います。





















多くのお客様から口コミもいただいております。
コウモリの駆除については私たちにお任せください!
まとめ
コウモリを家で見つけたら住み着いているのは1匹とは限りません。
コウモリは群れで暮らす動物なので、1匹見つけたら他にもいる可能性が高いです。
また見つけたとしても、自力で闇雲に対処するのは危険です。
理由として下記が挙げられます。
- 法律に抵触するリスクがある
- 攻撃されて怪我をする恐れがある
- 怪我や感染症のリスクがある
- 侵入経路封鎖時には高所作業を伴う
上記のようなリスクを避けるためにも、早期の段階で専門家への相談・依頼をオススメします。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |