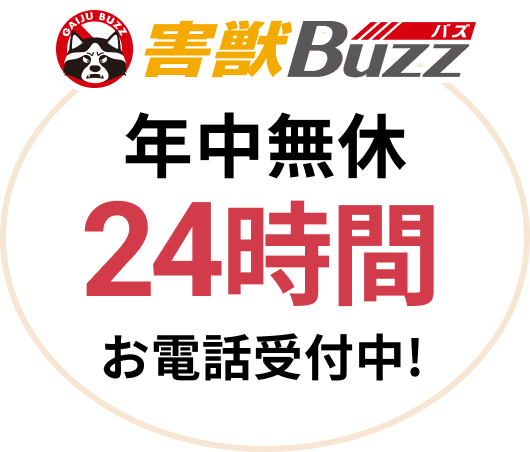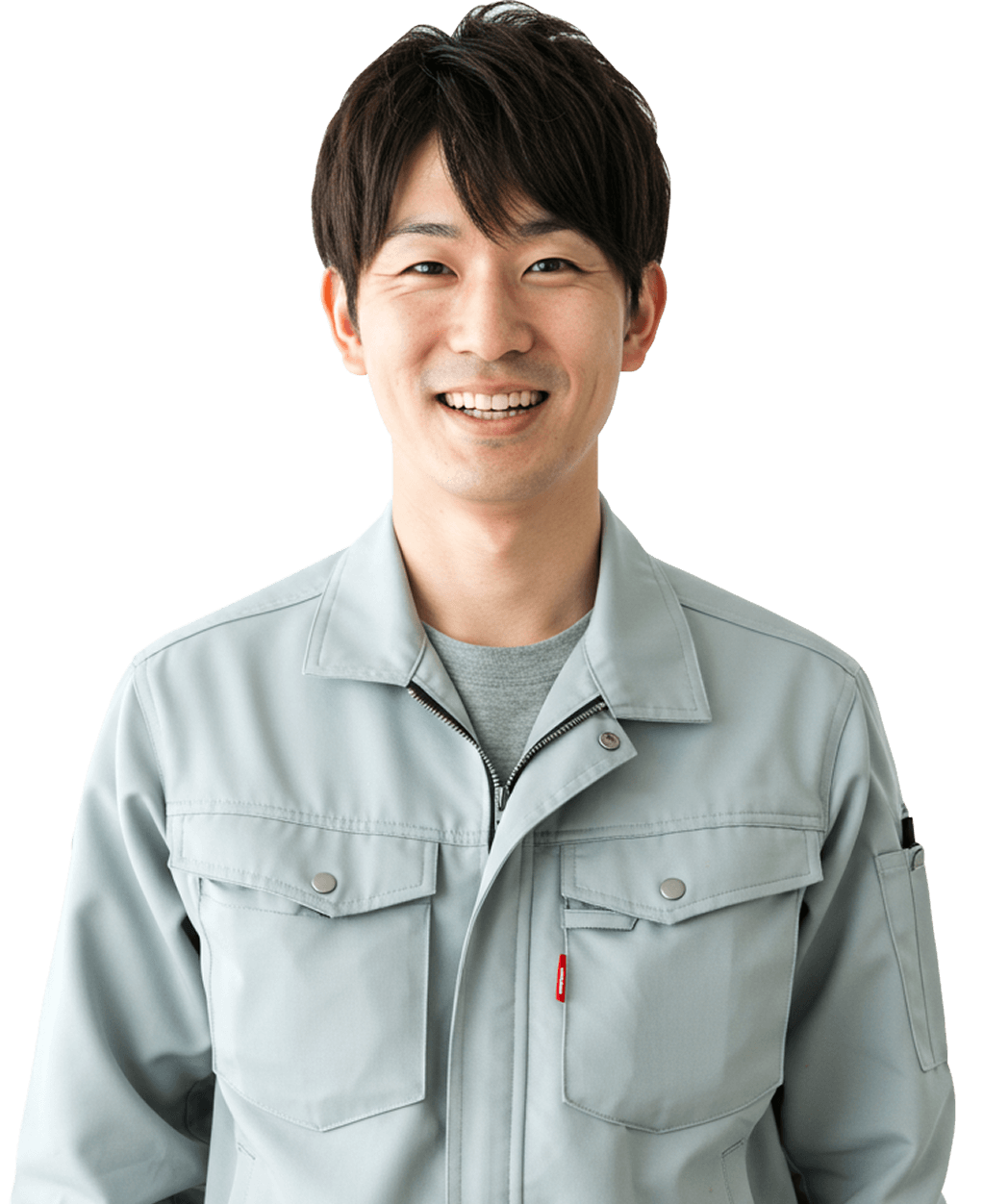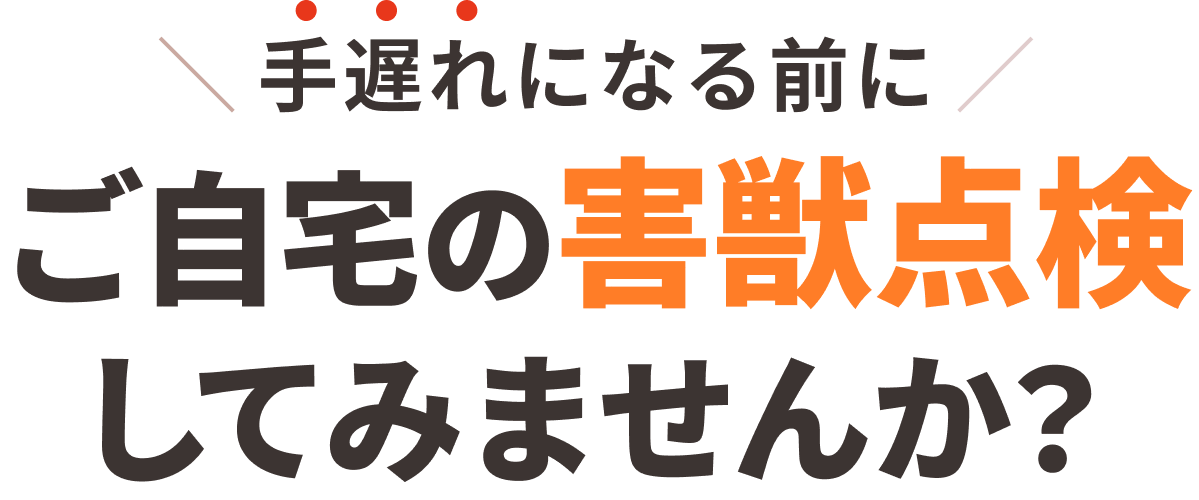アナグマの危険性を知らないと被害に遭うかも!対策も解説
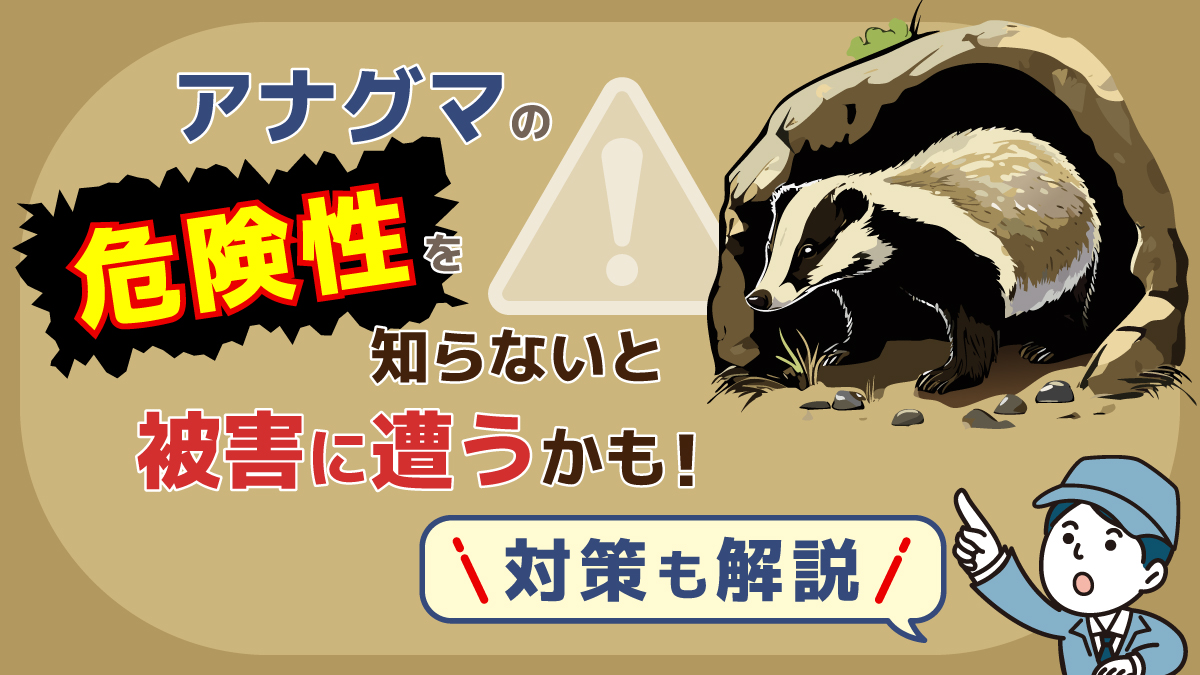
最近、住宅地の近くでもアナグマの目撃情報が増えています。かわいらしい外見から、つい近づいてしまう人もいますが、実はアナグマは危険性がある野生動物です。アナグマと共存していくには、習性や危険性を正しく理解し、適切な対策を取る必要があります。
本記事では、身近になりつつあるアナグマの危険性について、実際にどのような被害があるのか、予防策や対処法についてもわかりやすくお伝えします。アナグマとのトラブルを未然に防ぎ、安全に暮らすための知識としてぜひお役立てください。
目次
実は危ない?アナグマの危険性

一見すると愛嬌のある姿で「かわいい」と感じられるアナグマですが、実は危険性のある野生動物です。
アナグマは基本的に臆病な動物ですが、追い詰められたり身の危険を感じたりすると、鋭い爪や牙を使って攻撃することがあります。人間が不用意に近づいたり、ペットが興味本位で接近したりすると、思わぬケガやトラブルを招きかねません。
それだけでなく、アナグマは、以下のような被害をもたらすこともあります。
- 穴を掘って建物を倒壊させる
- 農作物を食い荒らす
- 病原体の媒介となる
それぞれの被害について順番に詳しく解説します。
穴を掘って建物を倒壊させる
もともとアナグマは地中に穴を掘り、巣を作って暮らす動物です。特に柔らかい土や砂地など掘りやすい場所を好んで巣を作ります。住宅の床下や庭、物置の下などに侵入し、巣を作るケースが増加中です。
この習性が原因となり、建物の基礎や地盤が崩れ、床が沈んだり傾いたりする危険性があります。また、地中の水道管や配線が破損するケースもあり、被害が拡大する可能性も否定できません。
実際に、地方自治体にも「庭や倉庫の下に穴を掘られ、建物が傾いて困っている」といった相談が寄せられることがあります。
アナグマの巣穴による被害は決して軽視できません。見た目はかわいらしい動物でも、放置すると大きな被害につながる可能性があります。建物周辺に穴がないか日頃からチェックを行い、早めに対策を取ることが重要です。
農作物を食い荒らす
アナグマは雑食性の動物で、ミミズや昆虫を好んで食べますが、トウモロコシやイモ類、果物といった農作物も食べます。特に畑の土は柔らかく、アナグマが巣を作ったり餌を探したりするのに適した環境です。そのため、一度畑に入り込むと繰り返し被害が起こる可能性が高まります。
また、被害は単に作物を食べられるだけではありません。アナグマは地面を掘り返す習性があるため、苗や根が引き抜かれ、畑全体が荒れてしまうことも珍しくありません。
アナグマが畑や家庭菜園に現れた場合、早期に対策を取らないと被害が拡大します。作物を荒らすだけでなく、畑そのものが使えなくなるリスクもあるため、防護柵を設置したり、忌避剤を使用したりするなど、具体的な対策を取りましょう。
病原体の媒介となる
野生動物であるアナグマは、さまざまな病原体や寄生虫を保有している可能性があります。特に注意が必要なのは、アナグマが持つことのある以下のような感染症です。
- レプトスピラ症
- サルモネラ症
- 狂犬病(国内では発生していませんが海外では報告あり)
こうした感染症は、アナグマとの接触だけでなく、糞尿や掘り返された土壌を介して間接的に感染するケースもあります。特に子どもやペットは興味本位で近づきやすいため、感染のリスクが高くなります。
アナグマが媒介する感染症のリスクを甘く見てはいけません。姿を見かけた際は決して近づかず、糞尿などの痕跡があれば速やかに適切な処理を行うことが大切です。感染症の危険を防ぐためにも、早めの対策が必要です。
アナグマ被害はどう防ぐ?対策を解説

アナグマによる被害を防ぐには、以下の3つの対策が有効です。これらの対策を日頃から意識し実践することで、安全で快適な生活環境を維持できます。
- 苦手なニオイで追い出す
- 柵・ネットで封鎖する
- エサを置かない
上記3つの対策をバランスよく実践することが重要です。ここからは、上記3つの対策について順番に詳しく解説します。
苦手なニオイで追い出す
アナグマを追い払うためには、「苦手なニオイ」を利用する方法が有効です。特定のニオイを忌避剤として活用すれば、アナグマが住宅や畑に近寄らなくなり、被害を効果的に防げます。
アナグマは嗅覚が非常に発達しており、鋭い嗅覚を使ってエサや安全な住処を探します。この嗅覚の鋭さが、逆に弱点にもなるのです。強い刺激臭や不快に感じるニオイがあると、その場所を危険または居心地が悪いと判断し、近寄らなくなります。
具体的にアナグマが苦手なニオイと、その活用方法を以下にまとめました。
- 木酢液:薄めたものを畑や庭周辺に散布する
- 唐辛子(カプサイシン):唐辛子エキスや粉末を散布する
- 市販の忌避剤:ホームセンターなどで販売されている動物用忌避剤を散布する
忌避剤を使用する際には、以下の注意点を押さえておきましょう。
- ニオイの持続時間は限られるため、定期的に再散布する
- 人やペットへの影響を避けるため、過度な使用や散布場所に注意する
- アナグマが慣れないよう、ニオイをローテーションで変える
安全かつ効果的にアナグマ対策を行うためにも、ニオイを使った対策を日常的に取り入れてみてください。
柵・ネットで封鎖する
アナグマ被害を防ぐためには、柵やネットを利用して物理的に侵入を防ぐ方法が非常に有効です。アナグマは一度安全な場所だと判断すると繰り返し侵入するため、確実に侵入経路を封鎖する対策が必要です。
アナグマは地面に穴を掘るのが得意な動物ですが、障害物を乗り越えたり破壊したりすることはあまり得意ではありません。そのため、柵やネットを設置して物理的に封鎖することで侵入を防げます。
柵やネットを設置する際には、アナグマが地中から掘って侵入しないよう、必ず地面の下に30〜50cm程度埋めることが大切です。
また、プラスチック製のネットはアナグマに簡単に破られてしまうおそれがあります。丈夫な金属製のフェンスや金網を使用し、侵入をしっかりと防ぎましょう。
さらに、アナグマは意外にも狭い隙間を通り抜ける能力があるため、ネットを選ぶ際はできるだけ目の細かいものを使うと安心です。
エサを置かない
アナグマは食べ物が豊富で安全な場所を好みます。住宅周辺にエサが豊富にあると、その場所を「エサ場」と認識し、頻繁に訪れるようになります。一度アナグマが食べ物を覚えてしまうと何度でもやって来るため、エサとなるものを徹底的に管理することが被害防止に有効です。
以下に、アナグマのエサとなりやすいものと、その管理方法をまとめました。
- 生ゴミ:密閉容器に入れて保管し、屋外に放置しない
- ペットフード:屋外で放置せず、食べ残しはすぐに片付ける
- 家庭菜園の作物:熟した果実や野菜は早めに収穫する
- 昆虫・ミミズなど:落ち葉や草を定期的に清掃して、虫が繁殖しないようにする
食べ物を徹底的に管理することで、アナグマが寄りつく理由をなくし、被害を未然に防ぎましょう。
アナグマ対策で知っておきたい注意点

アナグマ対策を行う際には、効果的な方法を実施するだけでなく、間違った対応を避けることも非常に重要です。
アナグマ対策で特に知っておきたい注意点は、以下の2つです。
- 自治体は駆除してくれない
- 捕獲には許可が必要
それぞれの注意点を順番に詳しく解説します。
自治体は駆除してくれない
アナグマによる被害が発生した場合、「自治体が駆除してくれるのでは?」と考える人も多いですが、実際には自治体が直接駆除を行うことは基本的にありません。
自治体が対応するのは、主に被害の相談窓口の紹介や対策方法のアドバイスに限られ、実際の駆除や捕獲については、住民自身で対策する、もしくは専門業者に任せるのが基本です。
そのため、住民自身が対策を講じる必要があることを理解しておきましょう。状況に応じて専門業者と連携して早期に対応することが、被害を最小限に抑えるポイントです。
捕獲には許可が必要
アナグマは「鳥獣保護管理法」によって保護対象となっている野生動物です。そのため、たとえ被害が出ていても、許可を受けずに個人で捕獲することは違法行為です。
違法捕獲をすると、法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。安全かつ合法的に対策を行うためにも、捕獲を検討する場合には必ず自治体に相談し、許可を得なければなりません。
自治体からの捕獲許可を取得する際の大まかな流れは以下のとおりです。
- 自治体(市役所など)に相談・申請
- 現地調査・審査:担当者による現場調査や被害状況の確認
- 捕獲許可の交付
- 指定された方法での捕獲
- 捕獲後の報告
捕獲許可を取得したうえで、専門業者に捕獲を依頼することが一般的です。
参考:e-GOV法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
アナグマ駆除はお任せください!
アナグマを見かけても、自分で無理に駆除しようとするのは非常に危険です。アナグマは法律で保護されており、対応には正しい知識と手続きが必要です。追い出しや駆除を行う際は、必ず専門業者に依頼するようにしましょう。
専門業者に依頼することで、安全かつ合法的にアナグマ対策を講じられます。例えば、以下のようなメリットがあります。
- 法律を遵守した適切な駆除方法で安心
- 侵入経路の発見と封鎖により、再侵入を防止
- 人体やペットに優しい手段での追い出し
- 糞尿の除去や消毒など、衛生面でも徹底対応
もし、どの業者に依頼すべきか迷った場合は、ぜひ「害獣BUZZ」にお任せください。アナグマを含むあらゆる害獣の駆除に対応しており、侵入経路の封鎖や清掃、再発防止まで一括でサポートいたします。
ご予算やご要望に合わせたプランをご提案し、多くのお客様から「安心して任せられた」との声を頂戴しています。365日24時間体制で対応しておりますので、アナグマ被害でお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
まとめ
アナグマは攻撃性こそ高くはないものの、巣穴による地盤の緩み、農作物の荒らし、病原体の媒介など、日常生活に多様な形で影響を及ぼします。
特に住宅地周辺では、エサ場や隠れ家となる場所が多く、いったん定着すると追い出すのが困難になります。また、対応を誤ると法律違反になる可能性もあるため、正しい知識と方法で対処することが重要です。
アナグマの存在に気づいたら、「放っておけばいなくなるだろう」と油断せず、被害が出る前に備えましょう。自治体への相談、環境整備、物理的対策など、できることから少しずつ始めることで、家や地域の安全を守れます。
害獣BUZZでは無料の現地調査を実施しておりますので、アナグマのような動物による被害でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
運営元情報
| サイト名 | 害獣BUZZ |
|---|---|
| 販売会社 | 株式会社リブシー |
| 代表取締役 | 金谷康生 |
| 電話番号 | 0120-987-601 |
| 所在地 | <関東本社> 東京都新宿区西新宿3-3-13-2F <埼玉支店> 埼玉県朝霞市上内間木262-5 <東海支店> 愛知県愛知県名古屋市港区秋葉1-28-1 <関西支店> 大阪府大阪市生野区巽中1-2-4-A <中四国支店> 広島県広島市中区本川町2-5-17 <神奈川営業所> 神奈川県横浜市中区太田町1-10 <岡山営業所> 岡山県岡山市北区中山下1-11-15-4F |
| 加盟協会 | (一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会 |